誰もが知らない読書の方法
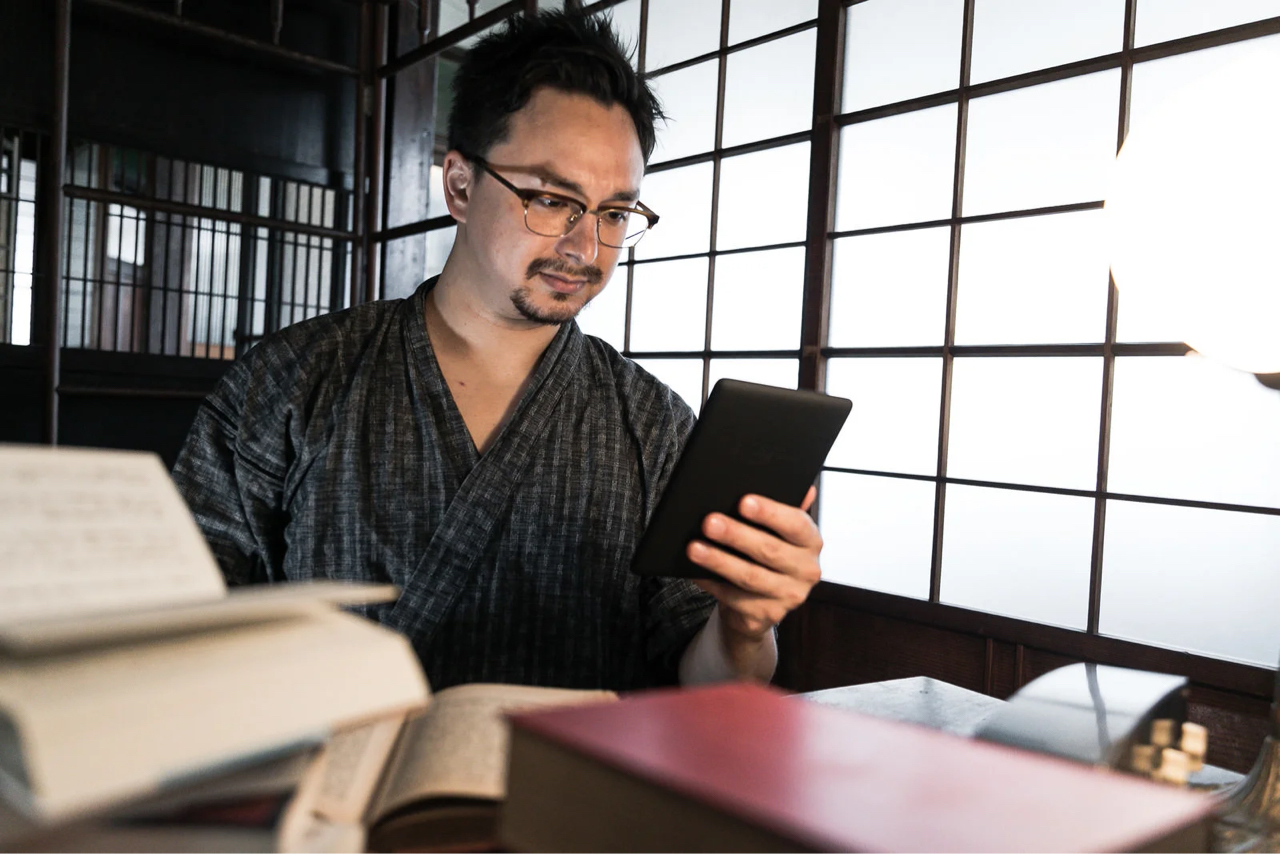
最近「オーディオブック派か、紙の本派か?」という話題が盛り上がっているのを耳にしました。
そしてふと、ある友人とのやりとりを思い出しました。
彼は移動中はオーディオブックを聞きながら、休日には紙の本を手にじっくり読書を楽しんでいます。
「通勤電車では耳、家では目。どっちかじゃなくて、使い分けるのがいい」と言う彼の話に、なるほどと膝を打ちました。
今回の記事では、「紙で読む」「耳で聴く」「紙と音声を併用する」3つの読書法を比較しながら、それぞれのメリット・注意点・おすすめの使い方について、科学的知見と実例を交えて整理していきます。
目次
読書スタイルは目的と状況に合わせるべきツール
読書の本質は、「情報を取り入れ、自分の中に残すこと」にあります。
しかし、その手段はひとつではありません。紙の本、電子書籍、オーディオブック──どれを選ぶかは、「何のために、どの状況で読むのか」によって最適解が変わってきます。
たとえば、紙の本は集中して深く読みたいときに向いており、オーディオブックは移動中や作業中など「ながら聴き」に適しています。さらに、文字と音声を併用すれば、記憶定着や理解の補強にもつながります。
この選択は、あえてたとえるなら「食事の道具」のようなもの。
寿司には箸、ステーキにはナイフとフォーク、カレーにはスプーンといった具合に、食べ物によって最適な道具があるように、読書もまた目的と状況に応じた「ツールの選択」が重要なのです。
読書とは何か?
そもそも、読書とは何を指すのでしょうか。
読書とは、単に文字を目で追う行為ではありません。それは「他者の思考や感情に触れ、自分の中で再構築する」創造的な営みです。
小説やエッセイのような文学作品に限らず、ビジネス書や技術書、あるいは日常的な報告書やメール文書であっても、「誰かが書いたものを読み、そこから意味を汲み取る」という点ではすべて読書といえます。
そこには、書き手と読み手の対話があり、人の意見に触れ、自分の視野を広げる旅ともいえる側面があります。
つまり、読書とは「他者の世界を通じて、自分の世界を広げる手段」でもあるのです。
学習効率や記憶への効果
紙の読書(視覚)は、じっくり読み込みたいときに圧倒的に強いです。
視線の戻し読みやページのレイアウト、ハイライトや書き込みといった「能動的な読み」ができるからこそ、内容の整理や記憶の定着がしやすくなります。
たとえば、難しい論文や技術書を読むとき。
途中で「ん?」と立ち止まって図を見返したり、数ページ戻ったり、こうした動作が自然にできるのが紙ならではのメリットです。
一方で、音声(オーディオブック)はリズムよく聞けるぶん、感情やストーリーの流れをつかむのに向いています。
特に移動中や家事の最中など、ながら聞きにはぴったり。
ただし細かい理論や数字を正確に覚えるのには不向きな面もあります。
そして紙と音声の併用。
これは「文章を見ながら音も聞く」というマルチモーダルと呼ばれるスタイルで、特に語学学習や読字障害のある人にとっては非常に有効です。
視覚と聴覚の両方を使うことで理解を助けたり、文字と音の対応を学ぶうえでも効果的です。
ただし、健常者が学習目的で併用した場合、かえって集中を妨げるケースもあるため注意が必要です。
たとえば、音声のスピードと自分の読むペースが合わないとストレスになったり、音と文字がズレたときに注意が分散してしまうことがあります。
また、耳と目の情報がぶつかることで、かえって処理が混乱し「読むことにも、聞くことにも集中できない」と感じる人もいます。
特に、情報量が多い専門書や抽象的な文章では、負荷が倍増して理解力が落ちるという報告もあります。
そのため、自分に合うかどうかを試したうえで、目的や場面に応じて使い分けるのがベターです。
仕事での活用
ビジネスシーンでは、紙での読書がやはり王道です。
重要な報告書、統計、マニュアルなど、情報の正確な把握が求められる場合、紙の資料を使った読書が最も信頼できます。
書き込み・付箋・マーカーなど、整理と記憶のための余白があるのもポイントです。
ただし、通勤時間や隙間時間には音声読書も強い味方。
たとえば営業マンが移動中に業界の最新情報をオーディオブックでインプットしておく、というのは非常に有効な使い方です。
注意点としては、重要な内容は後で紙にメモを残したり、要点だけ書き出しておくと記憶への定着が高まります。
また、プレゼンや会議の準備のときには、紙に書いた内容を「音読」してみるのも効果的。
これはプロダクション効果と呼ばれ、記憶に残りやすくなる方法です。
黙読だけでなく、自分の声で確認することで、内容の穴にも気づきやすくなります。
自分に合った読書法を見つける
読書法に正解はありません。
重要なのは、自分の情報処理スタイルに合った方法を知ることです。
視覚優位型の人
紙の読書が最も相性が良いです。
目で見て、構造を把握し、印をつけたりメモを取ったりしながら読むことで、理解が深まります。
聴覚優位型の人
音声読書がしっくりきます。
人の声を通じて情報を得る方が記憶に残る傾向があり、講義やインタビューも得意なタイプです。
集中が続きにくい人、読字が苦手な人
紙+音声の併用が効果的です。
音を手がかりにして目の動きをつなぎ止めるスタイルは、ADHD傾向の方や子どもにも有効です。
たとえば、「耳で聞きながら、目で文字を追う」という読書スタイルを実践した知人は、「読み飛ばし癖が直り、以前より読書が楽しくなった」と話してくれました。
読書が苦手という人こそ、音と目のセットを試してみてください。
ジャンル別に使い分ける
ジャンルによっても向き不向きがあります。
紙で読むのが合う本
専門書、統計資料、ビジネス書、学習教材、構造が複雑な小説。
記憶・整理・参照のしやすさが必要な本は紙で。
音声で聞くのが合う本
小説、エッセイ、伝記、詩、演劇、軽めの自己啓発本。
感情のニュアンスや語りのリズムがある内容は音声で。
併用が効果的な本
語学学習書、詩集、子ども向けの絵本や読み聞かせ、英語多読教材など。
音と文字の両方で取り組むと理解が深まる本におすすめです。
まとめ:「読む」と「聴く」、どちらもあなたの武器になる
紙・音声・併用。どれが一番、ではありません。
それぞれの読書法には強みがあり、向いている場面があります。
⭐️ 集中して理解したいときは紙
⭐️ 移動中やながらには音声
⭐️ 苦手意識のあるジャンルや語学学習には併用
まずは自分に合うスタイルを見つけること。
次に、目的に応じて使い分けること。
それが、知識を自分の力に変える最短ルートです。
あなたにとっての「読書の正解」は、あなたの生活と好奇心の中にあります。
それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!




