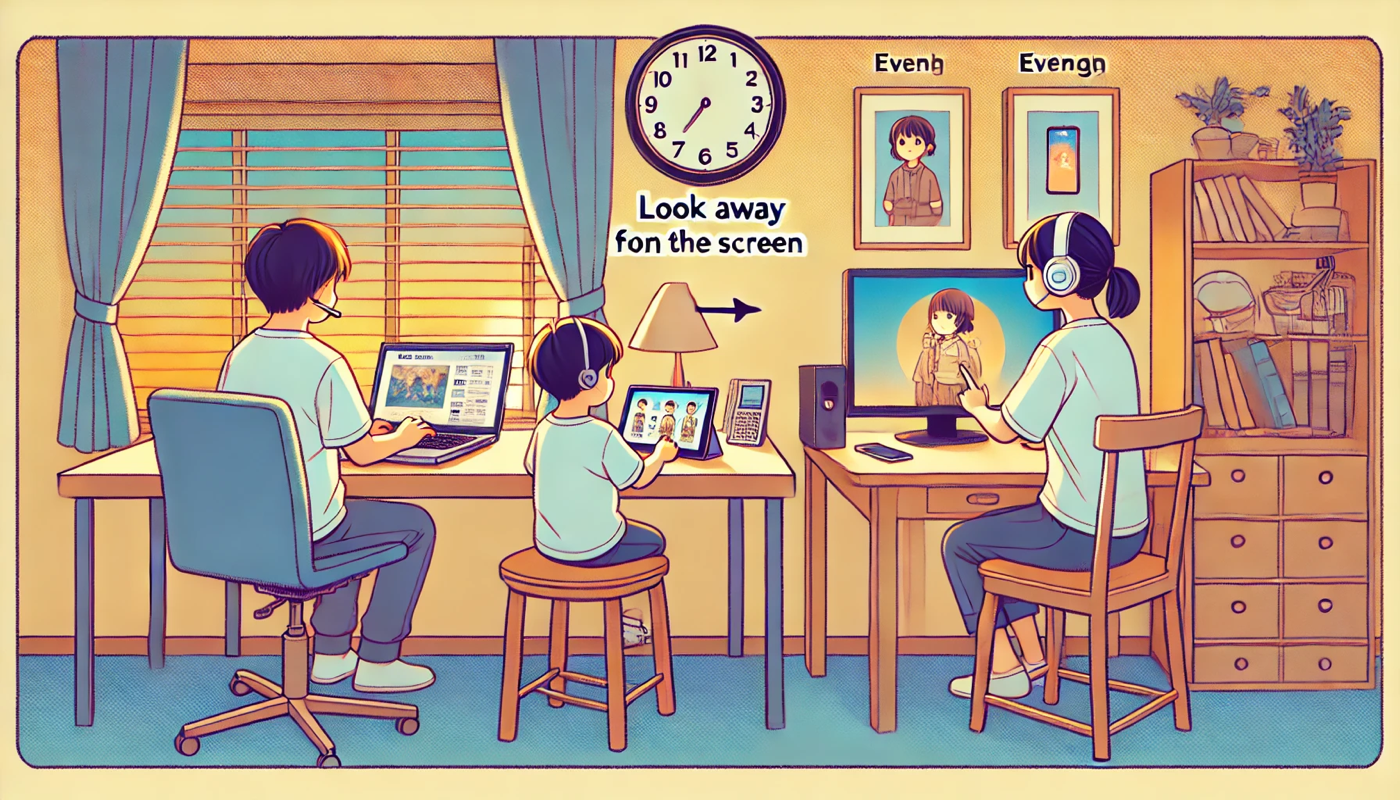あなたはあなたが食べたもの

唐突ですが、最近は、どんな食事をされていますか?
栄養に気を使っているはずなのに、疲れやすい、眠れない、イライラする、風邪をひきやすくなった……。
肌荒れや冷え、便秘、アレルギーといった不調を抱える人が、年々増えているように感じます。
でもそれは、年齢のせいでも、気のせいでもなく、私たちの身体が食べたものによってつくられているからかもしれません。
今回の記事では、「私たちの身体は、何でできているのか?」という原点に立ち返り、食べ物がどのように体調や気分に影響を与えているのかを、食材の背景や飼料、栄養価といった観点から紐解いていきます。
目次
あなたは、あなたが食べたもの
You are what you eat. あなたは、あなたが食べたものです。
これはフランスの美食家ブリア・サヴァランの言葉です。
この言葉が語るように、私たちの肌も、血液も、内臓も、すべては日々の食事によってつくられています。
食べたものは消化され、栄養として吸収され、血液に乗って全身の細胞へと届けられていきます。
良い栄養は、良い血液を生み、健やかな身体を支えます。
逆に、栄養の偏った食事やジャンクフードを続ければ、身体はその「質」に応じて、疲れやすく、乱れやすくなってしまうのです。
つまり、食べるものを変えることが、体調を変える最も確実な方法なのです。
そしてその意識の積み重ねは、やがて体質を変え、心の安定にもつながっていきます。
見えない栄養バランスが、不調の正体かもしれない
カロリーや量は足りているのに、体調がすぐれない。
そんなときは「質の偏り」を疑ってみてください。
ビタミンやミネラル、脂質、アミノ酸など、見えにくい栄養素のバランスが崩れると、気分や睡眠、代謝にまで影響を及ぼします。
たとえば、鉄、マグネシウム、亜鉛、ビタミンD、オメガ3脂肪酸の慢性的な不足は、冷え性や肌荒れ、疲労感、イライラなどの原因になることがあります。
さらに、血液は体内でしか作られません。
そしてその材料は、100%口にしたものから得られるのです。
「体質だから」「年齢だから」と諦める前に、まずは食生活に目を向けてみることが、根本的な改善につながるのです。
食材の質が、身体の質を左右する
「健康に良さそうなものを選んでいるのに、なぜか調子が悪い」
そんなときは、食材そのものの背景に注目してみてください。
たとえば
- その野菜は、どんな土で、どんな肥料で育ったのか?
- その肉や魚は、何を食べ、どんな環境で育ったのか?
- 加工や保存の過程で、どんな添加物が加えられているのか?
食材もまた「食べたものでできている」のです。
牛や豚、鶏、魚など、私たちが口にする命たちがどんなものを食べ、どのように育てられたかが、そのまま私たちの身体に影響してきます。
目に見える部分だけで判断するのではなく、育ち方にまで意識を向ける視点が必要です。
肉や魚の「食生活」が、私たちの健康を左右する
たとえば、牧草を食べて育った牛(グラスフェッド)は、オメガ3脂肪酸やビタミンE、共役リノール酸が豊富で、栄養価が高いことで知られています。
一方で、穀物飼育の牛(グレインフェッド)はオメガ6系脂肪酸が多く、現代人に多い炎症体質の一因になるとも言われています。
豚や鶏も同様で、飼料や飼育環境によって肉の栄養価や脂の質が変わります。
亜麻仁や海藻などを含む餌で育った動物の肉や卵は、オメガ3が豊富で、より健康的です。
魚もまた、天然と養殖では脂質のバランスが異なります。
天然魚はオメガ3が多い反面、重金属の蓄積には注意が必要。
一方、養殖魚も近年は飼料の改良や管理が進んでおり、栄養価と安全性の両立が可能になっています。
環境が変われば、味も変わる
食材の「味」や「安全性」も、育った環境や餌によって大きく左右されます。
放牧された動物はよく動くことで筋肉が引き締まり、旨味が強くなります。
一方で、魚粉を多く含む餌を与えられた鶏は、卵や肉に独特のにおいが出ることもあります。
また、ホルモン剤や抗生物質の使用も見逃せません。
こうした物質は私たちの身体だけでなく、抗生物質耐性菌といった社会的な問題にも関わってきます。
つまり私たちは、「肉を食べている」のではなく、「その肉が何を食べ、どう育ってきたか」という物語ごと、自分の身体に取り入れているのです。
「食べるものを選ぶ力」は、自分を守る力になる
食材の栄養価は、育て方や季節によっても変わります。
旬のものを選ぶことで、体のリズムにも自然と合いやすくなります。
まずは、こんな小さな一歩からはじめてみてください。
- 原材料表示をちょっとだけ意識して見る
- 産地や生産者の情報に目を留めてみる
- 「無農薬」「放牧」「天然」などの表示に興味を持ってみる
さらに、同じ野菜でも品種や育ち方によって栄養価が異なります。
いろいろな種類をローテーションすることで、栄養の偏りを防ぐことができます。
ほんの少しの意識が、身体を整え、気持ちを穏やかにし、暮らしを変えていく。
そんな力を、私たちはすでに「選ぶ」という行為の中に持っているのです。
まとめ:「食べ物の背景」と「自分の身体」を結ぶ
私たちが食べたものは、血となり肉となり、やがて心の材料にもなっていきます。
そして、その食べ物もまた、何かを食べて、誰かに育てられてきました。
食と向き合うということは、ただ健康を意識するだけでなく、自然や生産者、環境とのつながりを意識することでもあります。
「どこで、どう育ったのか?」
「何を食べてきたのか?」
そうした背景に目を向けながら、食材と丁寧に向き合うこと。
それは、まさに自分自身を大切にするということなのです。
そしてその選択が、家族の健康を守り、地球環境への配慮となり、生産者との信頼にもつながっていきます。
それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!