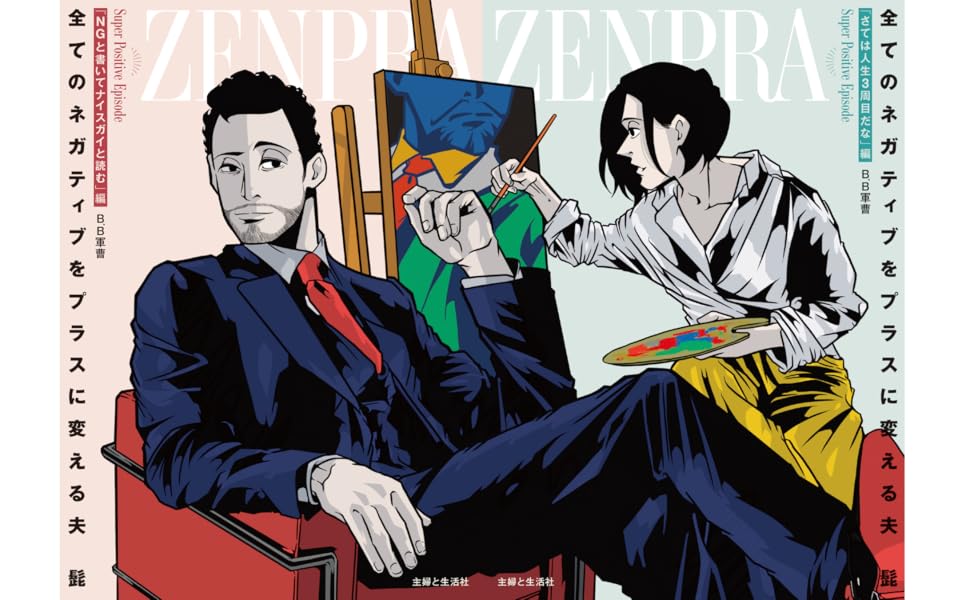2025年5月に読んだ本

今月もたくさんの刺激を受けました。
今回はその中から、特に印象に残った7冊をご紹介します。日常に深みを与え、考えるきっかけをくれるような本ばかりです。
気になるものがあれば、ぜひ手に取ってみてください。
ちなみに、X(旧Twitter)では毎週木曜日に小説の紹介もしています。ブログとあわせて、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。
著者:喜多川泰
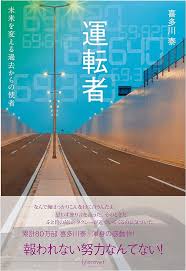
「運が良い人」と「運が貯まる人」は、まったく違う。
そんな気づきから始まる一冊。読み終えてまず感じたのは、「もっと上機嫌で生きよう」という静かな決意でした。
本書では、運をスピリチュアルではなく「日々の行動の蓄積」として描いています。
誰かのために動くこと、感謝を言葉にすること、自分の機嫌を自分でとること。
そのすべてが運を貯める行動になるという発想は、まさに現代を生きる私たちへの行動哲学。
特に響いたのは、「本当のプラス思考とは、自分が生きている間にどれだけこの世界にプラスの影響を与えられるかを考えること」という一文。
薄々そうありたいと思っていた自分の人生観が、言語化されたようで鳥肌が立ちました。
著者:デイヴィッド・ローベンハイマー / スティーヴン・J・シンプソン
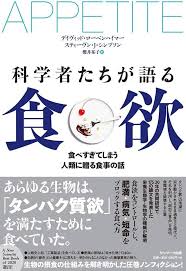
「なぜ人は食べすぎるのか?」を、進化生物学や栄養生態学の視点から解き明かす一冊。
中心となるのは「タンパク質レバレッジ仮説」。
人間はタンパク質を求めて食べ続ける性質があり、それが現代の加工食品と噛み合わないために過食が起こるという考え方です。
しかし最終的には「バランスがすべて」。
どんなに正しい知識があっても、それをどう活かすかは日々の試行錯誤。
変化を恐れずに、今の自分に合う食を選び取っていく勇気をもらいました。
著者:今井むつみ
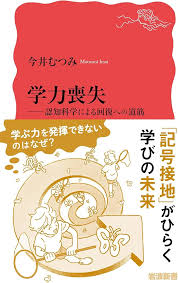
「記号接地」というキーワードがとにかく印象的。
子どもたちの学ぶ力が発揮されないのは、知識が具体的経験と結びついていないからという指摘に深く納得。
学力の問題は本人の能力ではなく、教育環境にある。
これは子育てや教育に関わるすべての人にとって、心に留めておくべき視点。
大人の学びにも通じる内容で、「学びは設計次第でよみがえる」と信じたくなる一冊でした。
著者:古賀史健
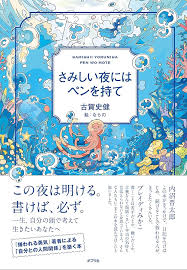
書くことは「自分を救う」行為。
そんな思いを改めて実感させてくれる、優しく力強い一冊。
特に印象に残ったのは、「今の自分を記録することは未来の自分を支える行為である」という言葉。
誰かに見せるためではなく、自分と向き合うために書く。
心のもやもやが言語化されることで、はじめて癒しが始まる。
書くことの意味がこんなに深いとは思いませんでした。
その日のうちにデジタル日記を手書き日記に変えた理由が、この本には詰まっていました。
著者:羽田圭介
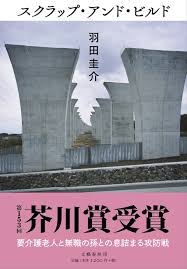
祖父の「早う死にたか」にどう向き合うかを描いた、切実で皮肉な家族小説。
介護というテーマを通して、本音と建前の狭間を鋭く突いてくる作品です。
読みながら、自分が年老いたときのこと、家族にどう見られるかということまで考えさせられました。
子育てにも通じる「どこまで本人の意志を尊重するか」という葛藤が、リアルすぎて胸に刺さります。
人の老いと向き合うには、自分自身の生き方も問われるのだと実感。
著者:獅子吠れお
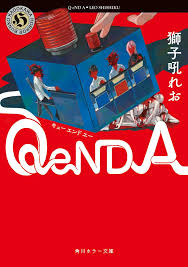
クイズ×異能×デスゲーム。まさに“B級なのに面白い”を地で行く小説。
高校生たちが異能力を持ってクイズに挑む設定は、設定だけ聞くと陳腐ですが、展開が意外に緻密で最後まで飽きずに読めました。
個人的にクイズが好きなので、物語とは関係ないクイズの技術解説にもワクワク。
新人作家の勢いが詰まった一冊で、読後感はとても爽快でした。
ミステリー・パズルMURDLE(マードル): 謎に包まれた100の事件の真相を解明せよ! (暫定⭐︎4.5)
著者:G・T・カーバー 他
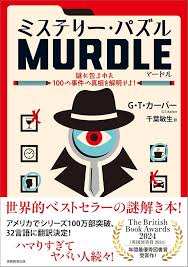
「殺人事件 × 謎解き × ロジックパズル」という夢の三拍子が詰まった問題集。
まだ全問は解ききれていませんが、毎日ちょっとずつ進めるのが楽しみで仕方ない。
推理というよりは論理クイズに近く、グリッドを埋めていく感覚がたまりません。
ミステリ好きというより、論理的思考を鍛えたい人、ボードゲームが好きな人におすすめです。
自分が探偵になったような気分を味わえる、一味違った読書体験でした。
⭐️ まとめ
本を読むことは、自分の世界を広げること。そのことを再確認させてくれる一ヶ月でした。
それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!