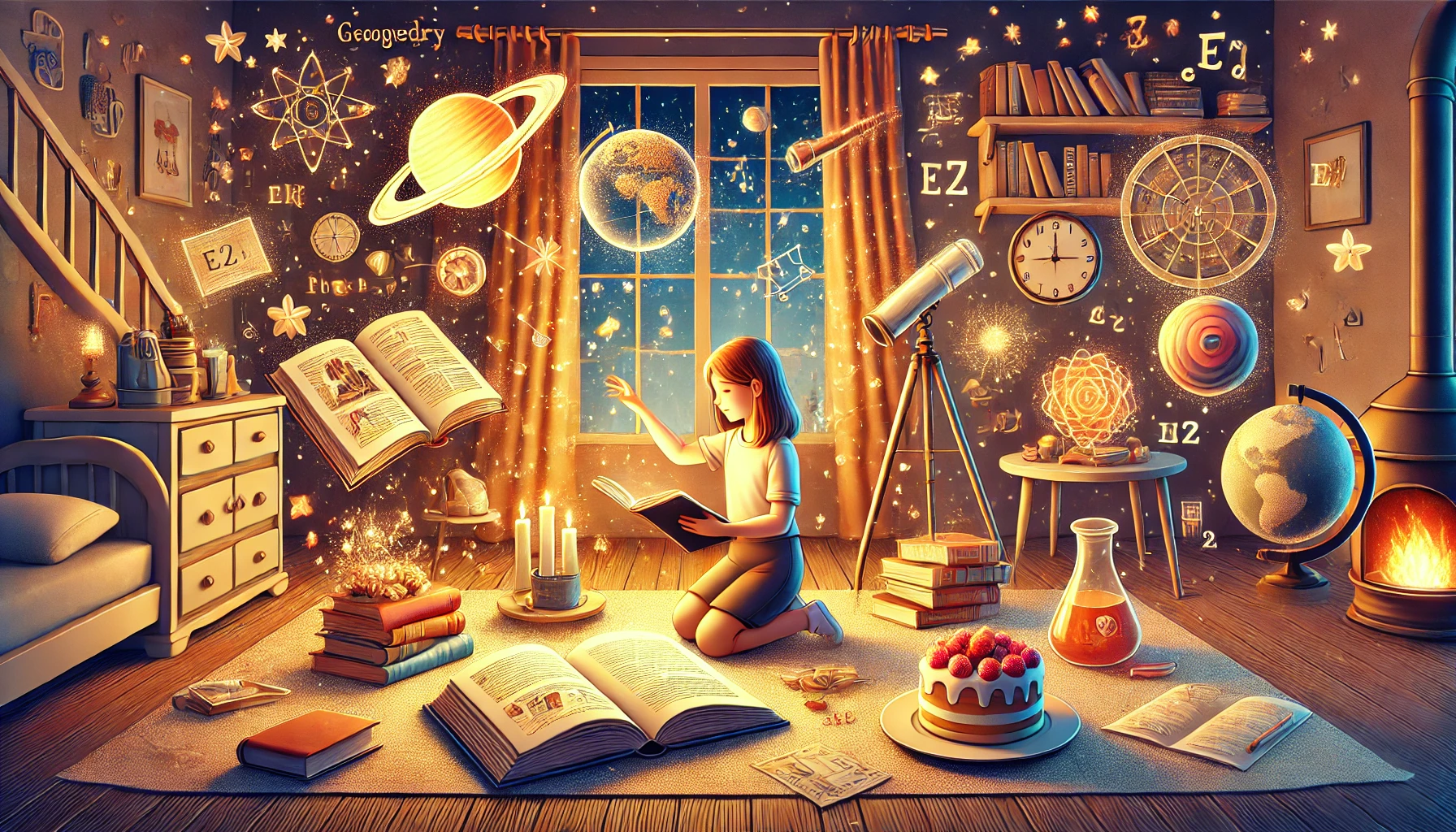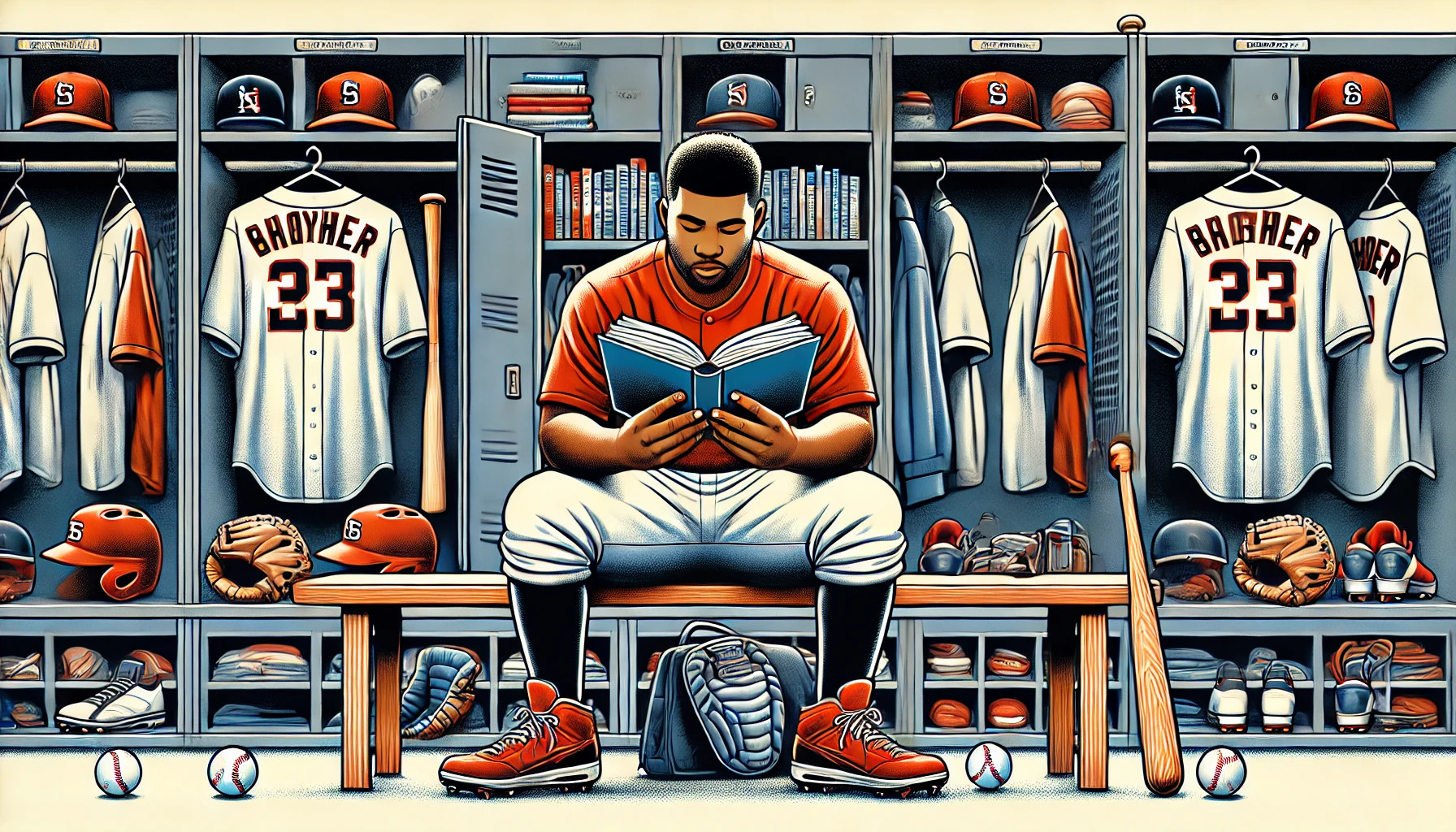嘘つきにならない、たった一つの方法
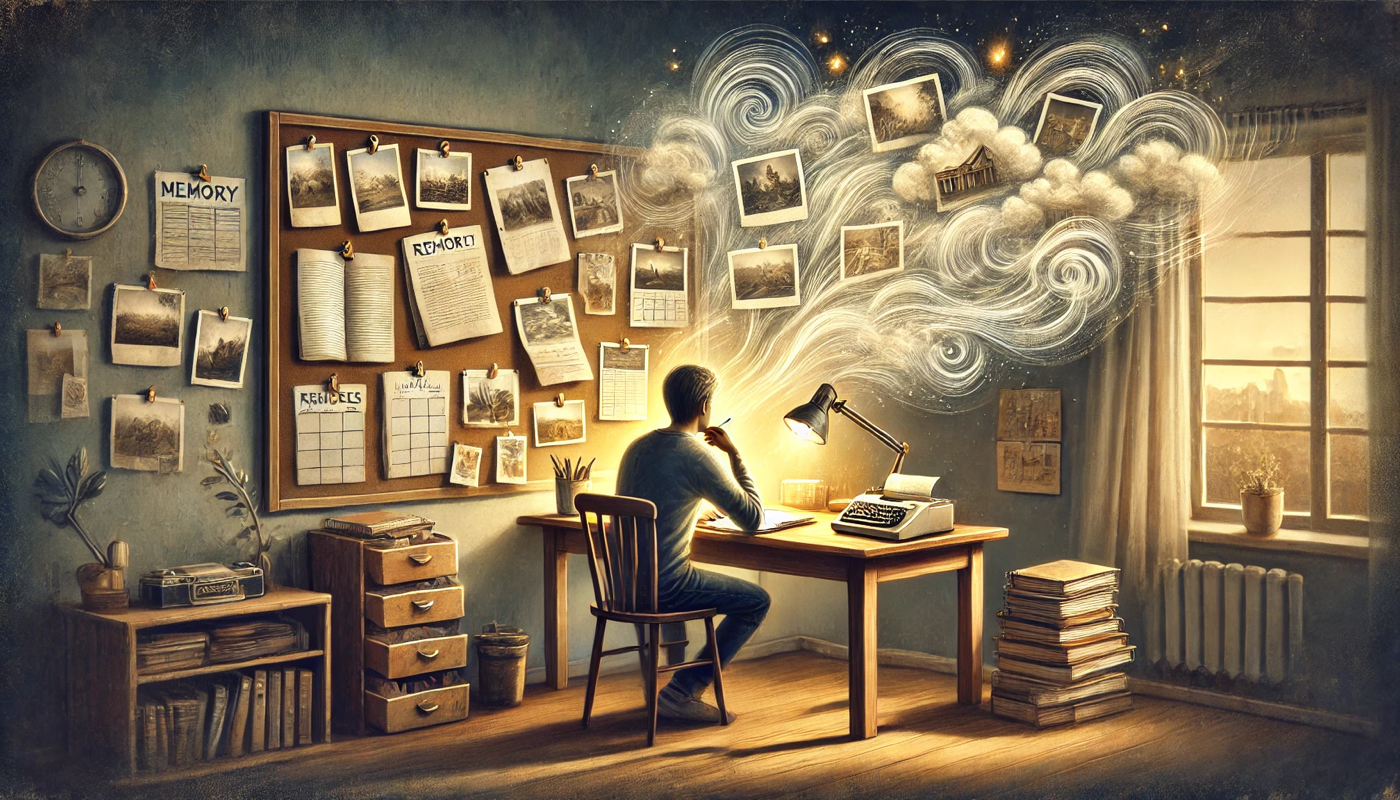
「また話盛ってない?」「それ、前と言ってること違うよ?」
私は、よく嘘つきだとからかわれる。
たしかに、性格的に話を大袈裟にしてしまうところはある。
でも、問題なのはそこではない。
実は、私は本気で「正しい」と思って、そう話しているのだ。しかも、自信満々に。
だけどそれが、まるごと記憶違いだったと知ると、恥ずかしさとともに恐ろしくなる。
自分の記憶を疑っていたはずなのに、なお「たぶん正しい」と思ってしまうのだから。
この現象、実は私だけのものじゃない。誰にでも、必ずあるのだ。
そんな経験から、今回の記事では「なぜ人間の記憶は曖昧で誤りやすいのか?」というメカニズムと、「ではどうすれば記憶違いによるトラブルを防げるのか?」という具体的な対策について、脳科学と実体験の両面から掘り下げて紹介していきます。
目次
記憶は真実の倉庫ではない
私たちは記憶を、まるでビデオ録画のように「正確に保存された過去」だと思いがちです。
でも実際には、脳は出来事の断片をその都度再構成し、現在の気分や思い込みと混ぜて「物語」として語っているに過ぎません。
この再構成のプロセスには、思い出すたびに情報が更新され、時には改変されるという特性があります。
つまり私たちが「覚えている」と感じることは、事実そのものではなく、感情・知識・先入観と混ざり合った最新版の物語なのです。
これは脳科学でも明らかにされています。
「記憶は記録ではなく、再創造される経験」なのです。
ジュリア・ショウの研究によれば、記憶の中にはしばしば作り話が含まれ、それを本人はまったく疑わないという実験結果も出ています。
記憶の確信度と正しさは無関係
ジュリア・ショウは著書『脳はなぜ都合よく記憶するのか』の中で、「記憶の鮮明さと正確性は、まったく別の問題である」と指摘しています。
つまり、「確信している=正しい記憶」ではないのです。
むしろ感情が強く関わる記憶ほど、知らず知らずに自分にとって都合のいい形に書き換えられるリスクが高まります。
強烈な印象やインパクトがある出来事は記憶に残りやすいものの、その詳細は後からの情報や人との会話、ニュースなどによって簡単に改変されてしまうのです。
脳は思い出すたびに記憶を編集していると言っても過言ではありません。
そしてその編集結果を、あたかも最初からそうだったかのように私たちは信じ込んでしまう。
この構造が、意図せず「嘘をついてしまう」原因になるのです。
遺伝子が記憶と性格に与える影響
東京大学・石浦章一教授の著書『遺伝子が明かす脳と心のからくり』では、記憶は脳内の可塑性(変化しやすさ)によって大きく左右されることが示されています。
脳のシナプス結合は日々変化しており、記憶は常に動的なプロセスの中にあります。
つまり記憶は「定着しているもの」ではなく、「更新され続けるもの」。
この可塑性が、学習や適応を可能にする反面、記憶の歪みや誤認の原因にもなるのです。
また、セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質の受容体の違いによって、「覚えやすさ」「意欲」「感情的な記憶の強さ」などにも個人差が出ます。
言い換えれば、記憶のクセは性格ではなく構造なのです。
私が導き出したたった一つの対策
こうしたメカニズムを知った私は、自分の記憶だけに頼って生きるのはあまりにも危ういと感じるようになりました。
そして導き出した唯一の答えが、「外部媒体に頼る」ということでした。
私はもともと、ブログを書く際に大量の文献や研究データ、本などを読み、それをノートやデジタルツールに記録しています。
何度も書き直し、確認し、他の資料と照らし合わせながら記事を仕上げる。
そして最近では、その習慣を日常生活にも応用しています。
誰かと話すときには、「それって確かこうだったよね」といった直感的な記憶に頼らず、「ちょっと待って、調べてみるね」と一度立ち止まる。
そして記録を確認したうえで、感情を込めて自分の意見を伝える。
これは面倒に感じるかもしれませんが、こうしたひと手間が「無意識の嘘つき」にならないための最大の武器になるのです。
記憶との上手な付き合い方
人間の記憶は、欠陥ではなく創造のための道具でもあります。
記憶の不正確さは、創造性を支え、他人の話に共感する余白を与え、経験を「意味ある物語」に仕立てる力を持っています。
だからこそ、「私はこう記憶しているけど、違う可能性もあるよね」と言える柔らかい姿勢が大切です。
自分の記憶を絶対視せず、「もしかしたら違っているかも」と一歩引いて考えることが、結果的に誠実さや信頼性につながります。
記憶は完全にはコントロールできません。
しかし、「記憶を信じすぎない」という姿勢だけでも、人間関係のトラブルや誤解を大きく減らすことができます。
さらに、以下のような具体的な習慣を取り入れることで、記憶との関係をより健全なものにしていけます。
- 大切な会話や出来事をすぐにメモに残す習慣をつける
- スマホのメモ機能やボイスメモを使って、その場の感情や状況も含めて記録する
- 他人との会話で記憶違いが起きたときは、「私の記憶ではこうなんだけど、違ってたら教えてね」と前置きする
- 人と話すときには、外部媒体(ノート・メモ・検索)を参照しながら正確な情報を確認して話す癖をつける
こうした行動は、記憶を外部に補完するだけでなく、自分の感情の流れや思考の傾向を見える化し、より柔軟で誠実な対話を可能にしてくれます。
まとめ:記憶に頼るな、記録に頼れ
記憶は完璧ではなく、感情や環境、遺伝的要因によって常に変化しています。
確信が強いほど危ういこともあり、自分の思い出は最新版の編集済み物語だと受け止める必要があります。
だからこそ、私たちができる最も誠実な行動は、「外部記録との二重構造」を築くこと。
記録を取り、記録を読み返し、それを土台にして人と関わる。
この習慣こそが、嘘つきにならず、自分にも他者にもやさしい生き方につながるのだと、私は今、ようやく確信しています。
それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!