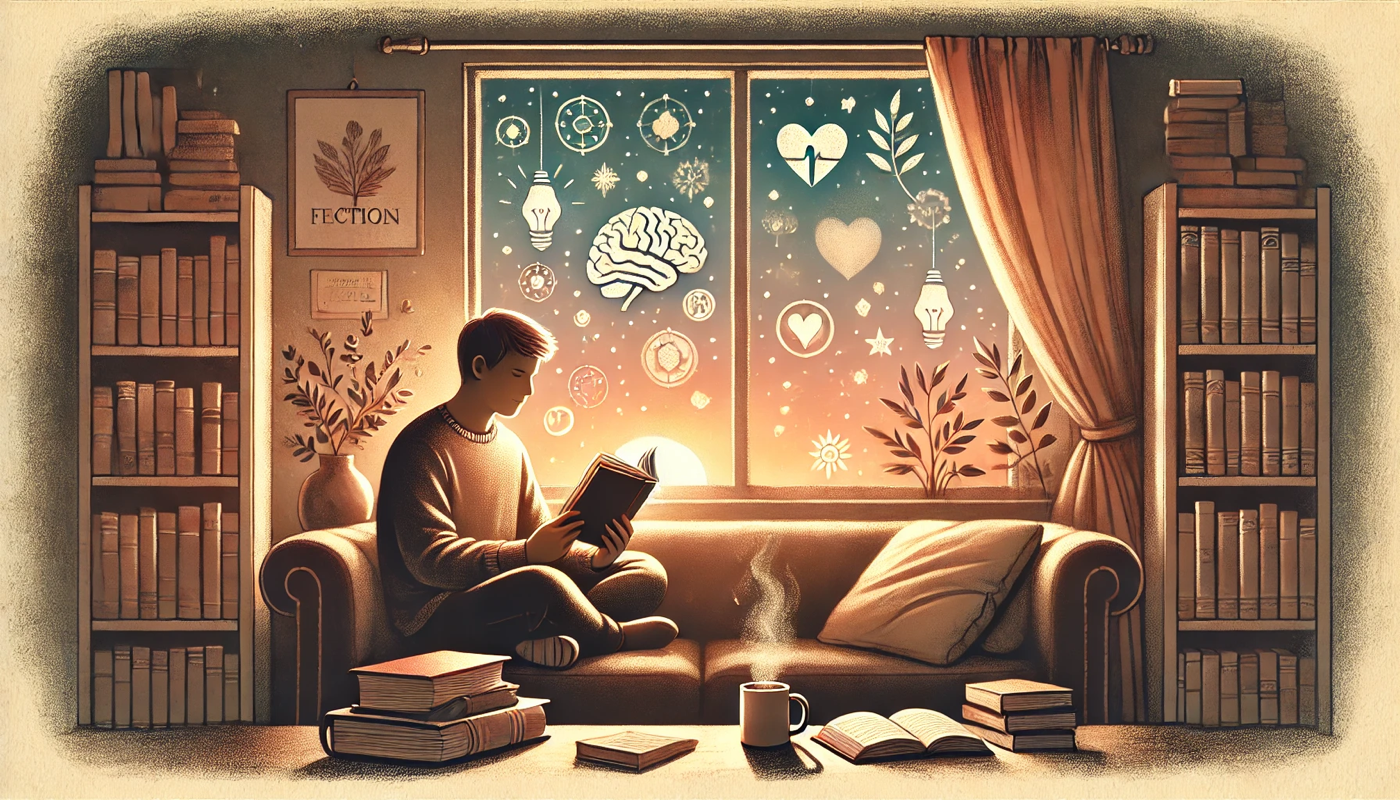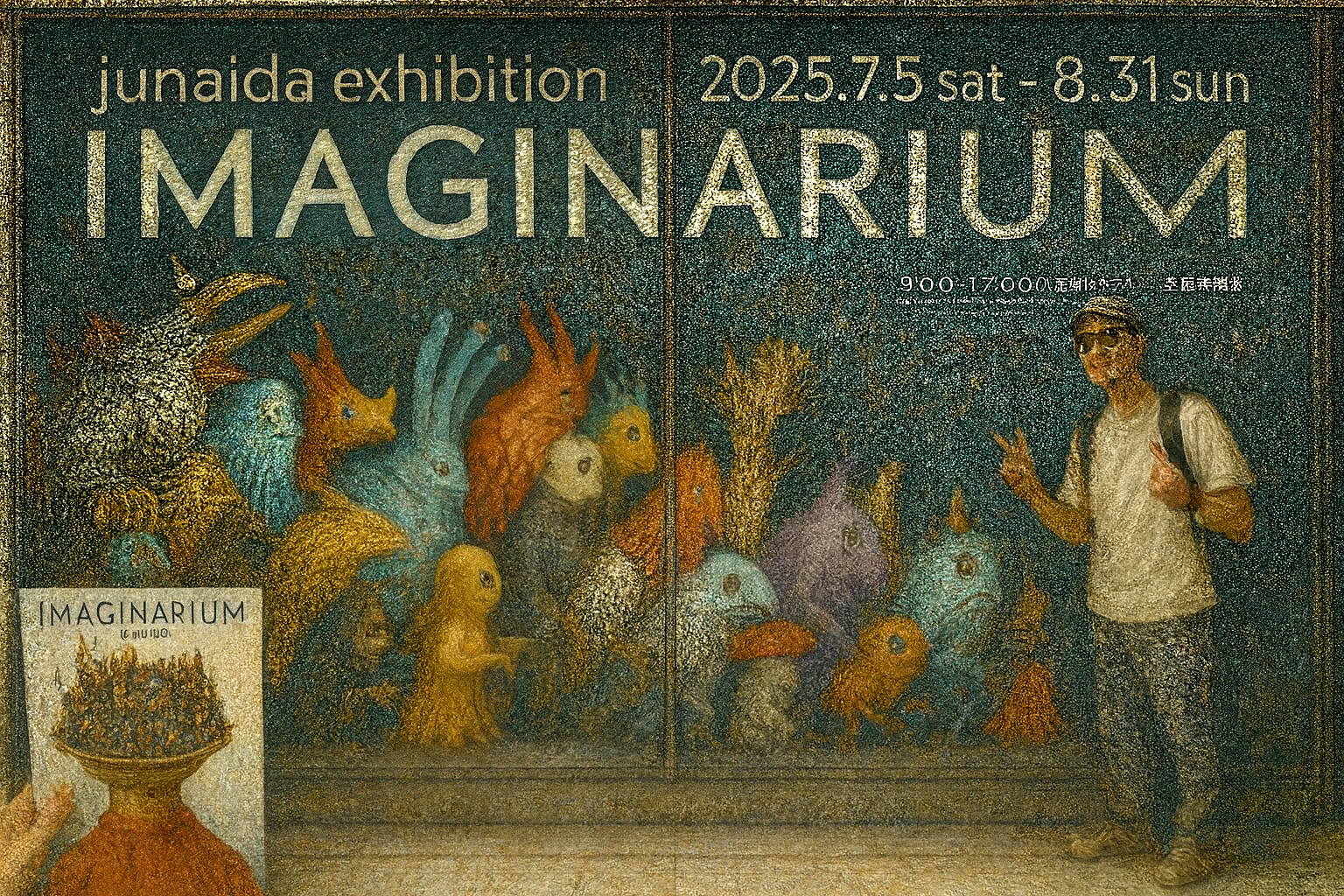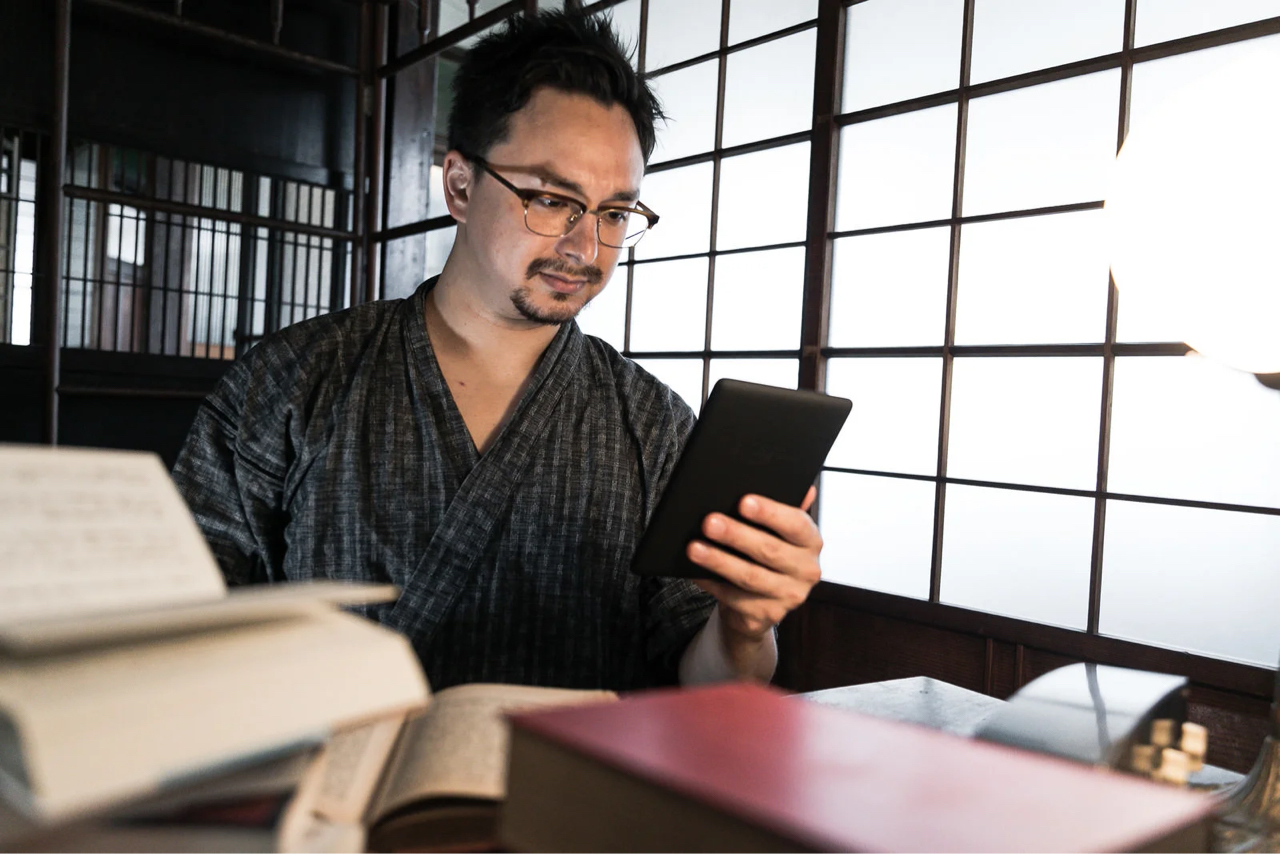忘れる脳、思い出せない私
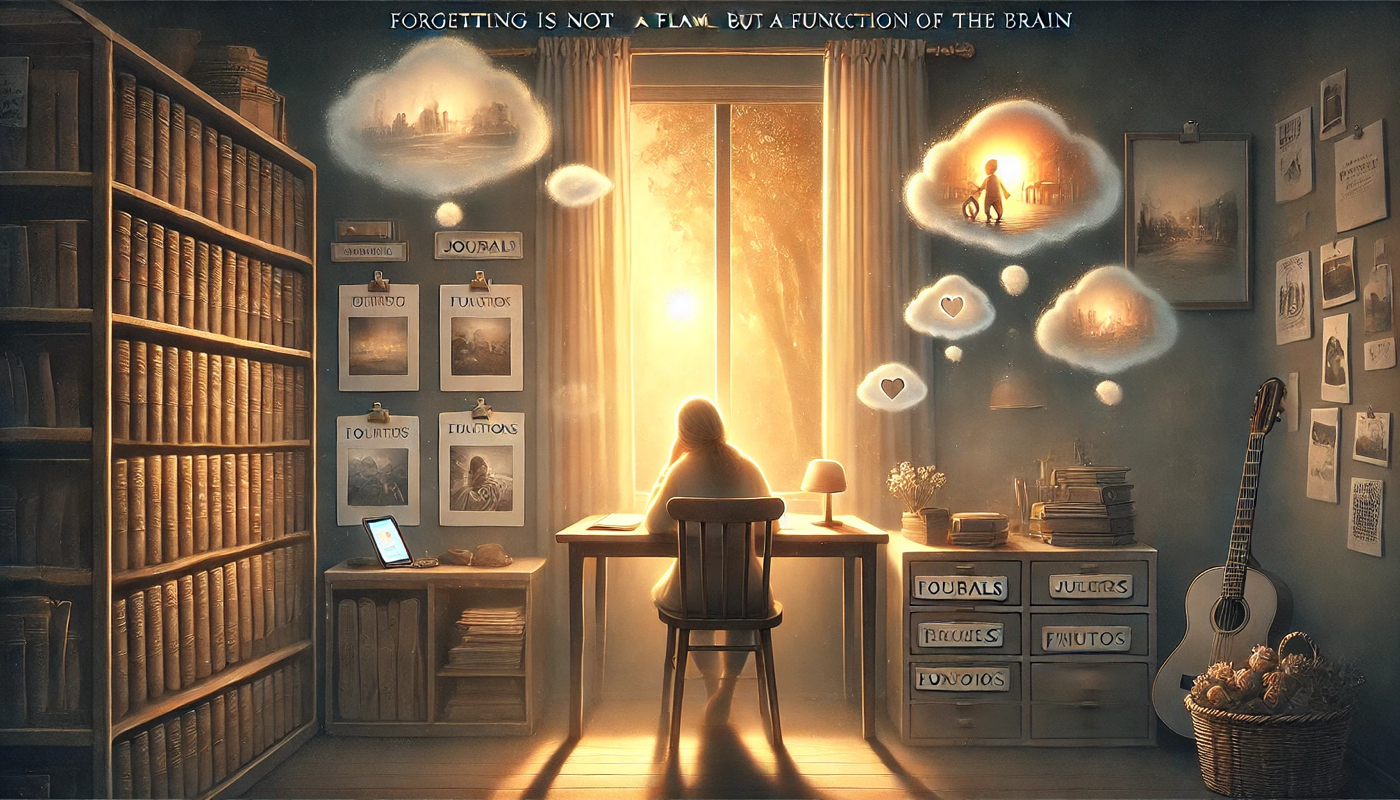
「あれ?旅行のとき、どこのお店に入ったんだっけ?」
「え、そんな話したっけ?」
家族旅行や子どもの行事、友人との何気ない会話。
どれも大切な記憶のはずなのに、ふとしたときに思い出せないことがある。
楽しくなかったわけでも、関心がなかったわけでもない。
むしろ、心が動いた瞬間の感情はちゃんと残っている。
でも「何を話したか」「どこに行ったか」など、肝心のディテールがスルッと抜け落ちている。
そんな自分を、以前の私は責めていました。
でも、最近わかったのです。
「忘れる」ということには、脳科学的にちゃんと意味がある。
むしろ忘れる能力こそが、人間らしさのひとつだということを。
今回の記事では、「なぜ人は忘れるのか」「忘れることの意味」「創造や感情との関係」について脳科学の視点から解説していきます。
目次
忘却はエラーではなく、最適化のための機能
私たちの脳は、膨大な情報に囲まれながら生きています。
見たもの、聞いたこと、感じたこと。
もしそれらすべてを完璧に記憶しようとしたら、処理が追いつかなくなり、逆に思考や判断が遅れてしまう。
そう考えると、「忘れる」ことは、脳が不要な情報を自動で整理してくれている行動なのです。
コロンビア大学の神経内科・精神医学教授のスコット・スモール氏は自身の著書『忘却の効用』で、「忘却は脳の防衛機能であり、情報の選別と再構築を可能にするクリエイティブな営みである」と明言されています。
すべてを記憶していたら、私たちは新しいことに集中できなくなる。
忘れることは、次へ進むための準備でもあるのです。
忘却のメリット
忘れることには、以下のようなメリットがあります。
感情の平穏
つらい記憶が永遠に残ることは、心に大きな負荷をかけます。
脳は時間の経過とともに感情のトゲを和らげることで、精神の安定を保とうとします。
創造力の源泉
すべてを正確に覚えようとすると、情報量が多すぎて脳が処理に追われ、かえって混乱しやすくなります。
また、記憶に忠実であろうとするあまり、既存の枠組みにとらわれ、新しい視点を持ちにくくなってしまうのです。
一方で、細部を忘れることで情報が抽象化され、「本質」や「印象」だけが残ります。
これにより、異なる知識や経験が柔軟に結びつきやすくなり、新しい発想やひらめきが生まれやすくなります。
柔軟な行動
過去に囚われすぎず、柔軟に物事を捉えるためには、ある程度忘れることが必要です。
これは、単なる精神論ではなく、脳の構造とも関係しています。
扁桃体と海馬
私の中でもっとも腑に落ちたのは、扁桃体と海馬の関係でした。
扁桃体は感情を司る脳の中枢。
そして海馬は記憶を処理・保存する器官です。
強い感情(たとえば楽しかった、悲しかった)は扁桃体に強く刻まれやすい。
一方で、細かい会話の内容や場所の名前などは、海馬が一時的に記憶した後、取捨選択されます。
つまり、「あの旅行はすごく楽しかった!」という感情は覚えていても、「何を食べたか」「誰が何を話したか」はすっかり忘れてしまう。
これは脳の仕組みによる正常な反応なのです。
それを知って、私は少し肩の力が抜けました。
覚えていないからといって、それは興味がなかった証拠ではない。
むしろ「感情が残っている」だけで十分尊いのです。
忘却にも個人差がある
東京大学の石浦章一教授の人気講義をまとめた講義録『遺伝子が明かす脳と心のからくり』では、記憶のしやすさ・忘れやすさには個人差があることが指摘されています。
- 海馬の大きさ
- ワーキングメモリの容量
- ドーパミンやセロトニンの受容体の感受性
これらはすべて遺伝的・神経化学的な要因であり、「覚えられない自分」を責めることは、ちょっと的外れかもしれません。
さらに、ストレス・睡眠不足・情報過多な生活習慣も、記憶の定着に大きな影響を与えます。
忘れることで「本質」が残る
もうひとつ、忘却の進化的なメリットとして見逃せないのが、「抽象化」の力です。
私たちは何かを経験したとき、そのすべてを覚えているわけではありません。
むしろ、細かい情報は忘れていくことで、共通点や要点が浮き彫りになる。
これが抽象化です。
たとえば、
- いくつもの旅先で楽しかったという感情は覚えていても、宿の名前やお土産の種類は曖昧
- 本を何冊も読んで、細かな理論や事例は忘れても、「人は認められたい」「習慣が人生を変える」といった核心だけは残る
これは脳が、雑多なディテールを捨て、共通するパターンや法則を残すように進化してきた証拠です。
この情報の圧縮によって、人はより速く判断し、別の場面にも応用できる「知恵」を獲得します。
つまり、「覚えていること=重要なこと」ではなく、「残ったこと=再利用可能なエッセンス」なのです。
忘れることを恐れるより、「何が残ったか」に意識を向けてみましょう。
そこにこそ、あなたの経験のエッセンスが詰まっているのです。
忘れても大丈夫。だからこそ、記録を残そう
私がたどり着いた結論は、「忘れることは悪くない。でも、残したいものはちゃんと記録する」ということ。
日記でも、写真でも、音声メモでもいい。
五感で感じたこと、心が動いたことを少しでも外部化することで、「忘れてしまっても、思い出せる」ようになります。
子どもとのやりとりや、ふと心が動いた瞬間をスマホでメモするだけでも、未来の自分にとってはかけがえのない記憶の補助線になるのです。
そして「記録」が必要なのは思い出だけではありません。
私は、人との約束や家族内での決まりごと、読書や講座でインプットした知識、思いついたアイデアなども、すべてメモしておくようにしています。
なぜなら、記録することで「これを忘れてはいけない」と脳に圧をかける必要がなくなり、安心して手放すことができるからです。
これは「ワーキングメモリ(作業記憶)の節約」という点でも非常に効果的です。
脳は「書き留めたから大丈夫」と判断し、その分の思考リソースをほかに回すことができるのです。
つまり、記録することは単に忘却を補う手段ではなく、むしろ「集中力や創造力を引き出すための戦略」でもあります。
だからこそ、ほんの一言でも、思いついた瞬間に外部化しておくことが、後々の自分にとって何倍にも価値をもたらしてくれるのです。
まとめ:「忘れること」も「思い出すこと」も、脳の味方にしよう
私たちは完璧ではないし、覚えていられないこともたくさんある。
でも、それは人間らしさであり、進化の知恵なのだと思います。
だからこそ、自分の記憶に優しくなっていい。
そして、必要なものは自分の外に残しておけばいい。
「記憶」は信じすぎず、「忘却」は責めず、「記録」と共に生きる。
それが、私がたどり着いた脳との上手な付き合い方です。
それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!