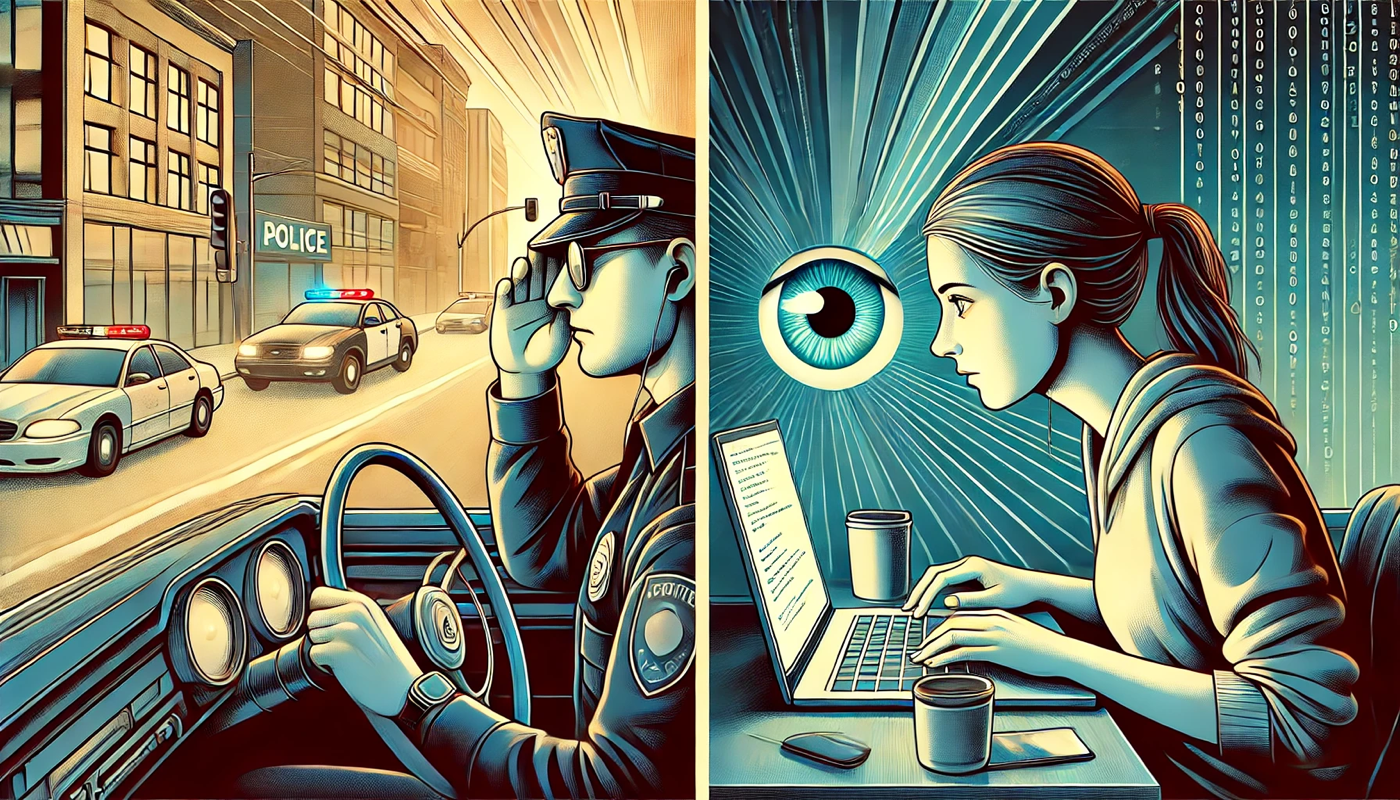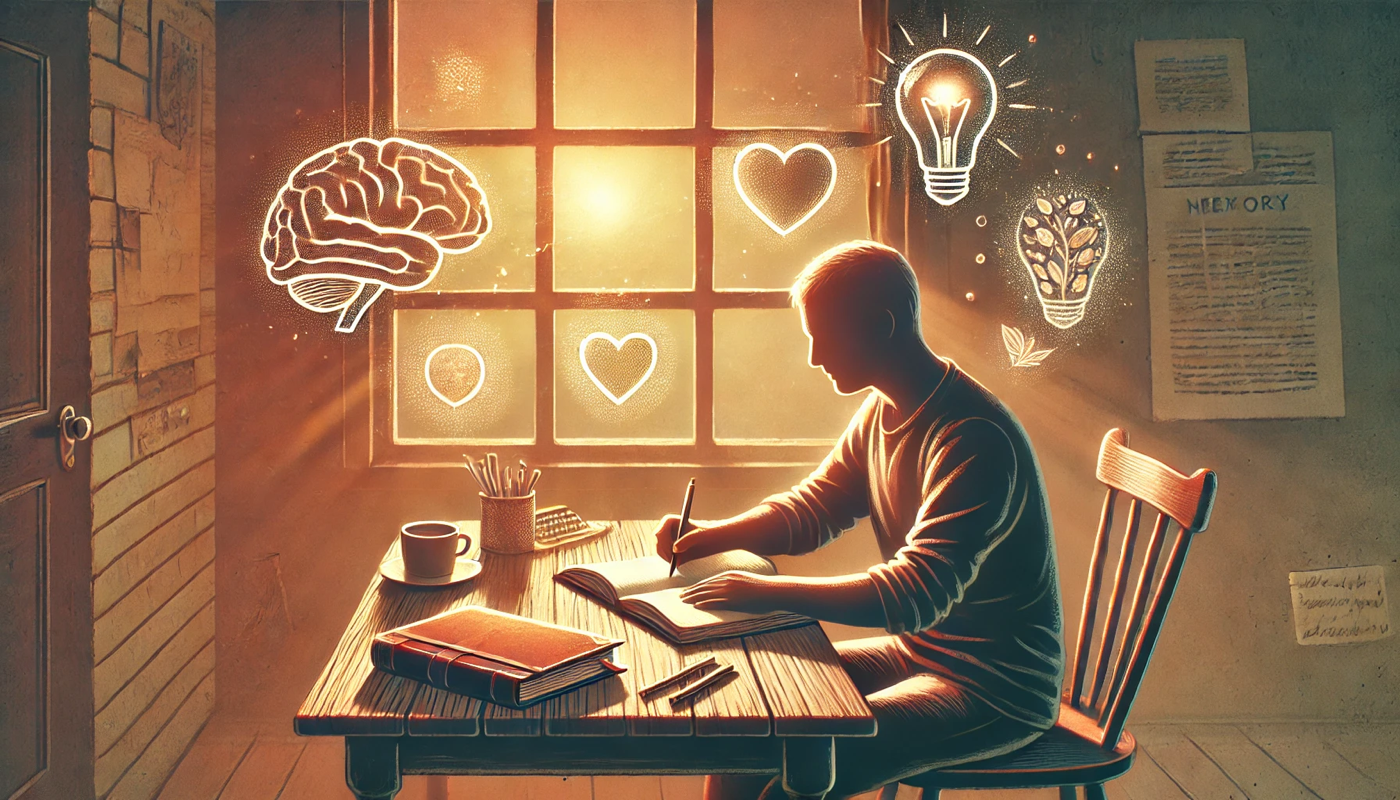何回説明しても伝わらないの正体

「何度言っても伝わらない」
「ちゃんと説明したのに、わかってもらえない」
そんなモヤモヤした経験、誰にでもあるのではないでしょうか。
でもそれは、あなたの伝え方が悪いのでも、相手の理解力が足りないのでもありません。
原因はもっと根深く、「脳の仕組み」にあります。
このすれ違いの正体を、認知科学の視点からわかりやすく解き明かしてくれるのが、今井むつみ先生が書かれた「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策という本です。
本書では、言葉を通じた理解のズレの背景にある「スキーマ(schema)」という概念を軸に、なぜ人は同じ話をしても違うように受け取るのか、どうすれば伝わる会話になるのかを、豊富な実例と研究をもとに説いています。
今回の記事ではその知見をもとに、「人はなぜわかり合えないのか?」「どうすれば他者理解が深まるのか?」という問いに、心理学・脳科学の視点から迫ります。
目次
スキーマとは何か?
本書のキーメッセージのひとつに、今井氏のこの言葉があります。
「人は現実そのものを見ているのではなく、記憶と経験から構築された仮想モデルを通して世界を理解している」
この仮想モデルの正体が、スキーマ(schema)です。
スキーマとは、過去の経験や知識をもとに脳がつくり出す、物事の「理解のテンプレート」。
たとえば、
- 「レストランでは、案内されて→注文して→会計する」という一連の流れ
- 「医者は白衣を着ていて偉い」
- 「自分はおとなしいタイプだ」
こうした前提知識や価値観の型のことを指します。
人は日々膨大な情報にさらされていますが、すべてを丁寧に処理するのは不可能です。
そこでスキーマを活用することで、効率よく「これはこういうことだろう」と判断できるわけです。
伝わらない理由は「スキーマの違い」にある
ところが、便利なはずのスキーマが、誤解やすれ違いを生む原因にもなるのです。
今井氏は、「伝える力」よりも「相手の頭の中のモデル(スキーマ)を読む力」が大切だと説きます。
なぜなら
- 人は、自分のスキーマに合わない情報は「ピンとこない」
- 説明されても、スキーマにマッチしなければ誤って理解してしまう
- 「当たり前」「普通」「常識」と思っていることは、自分のスキーマにすぎない
たとえば、子どもが「2分の1って何?」と聞いたときに、ピザを半分に切った図を見せて「これが2分の1だよ」と教える。
大人はわかるけれど、子どもにとっては「等しく分ける」という前提スキーマが育っていないため、意味が通じないことも多いのです。
この「スキーマの前提」が違うままいくら説明しても、すれ違うのは当然なのです。
記憶すら歪める「スキーマの罠」
スキーマは記憶の再構築にも影響します。
今井氏は、大学の講義で「500円玉の絵を描いてみてください」と学生に求めた実験を紹介しています。
日常的に見ているはずなのに、細部まで正確に描ける人はほとんどいない。
つまり「見たこと」と「記憶していること」はまったく別物だということ。
実際、人は見たものをそのまま記憶しているのではなく、「スキーマに合うように補完しながら」覚えているのです。
- オフィスに「本があるはず」と思い込んで、実際にはなかった本をあったと記憶する
- ホームレスの男性が襲われていたのに、「襲っていたのは彼だ」と誤って記憶する
こうした誤記憶の実験は数多くあり、私たちの記憶もまたスキーマによって加工・改変されていることを示しています。
他人のスキーマを読む力が、真のコミュニケーション力になる
本書が強調するのは、「正確に伝える技術」よりも「相手の心の中を想像する力」=心の理論(Theory of Mind)の重要性です。
- 「この人は何を知っているか?」
- 「どういう価値観を持っているか?」
- 「何に不安を感じているか?」
これらを想像しながら話すことで、初めて伝わる会話が生まれます。
そのためには、
- 感情を無視しない(感情と情報のバランス)
- 抽象だけでなく具体例も添える
- 「伝わらない」を前提に、対話を繰り返す
こうした姿勢が、コミュニケーションの質を根本から変えるのです。
具体的なアクションプラン
自分の「当たり前」にクエスチョンマークをつける
- 「なぜ自分はそう思うのか?」を日常的に振り返る
- 「普通◯◯でしょ?」という言葉が出たら、一度立ち止まる
自分と異なるスキーマを持つ人と会話する
- 年齢差・文化差・立場の違いのある人と対話する
- 意見が合わない相手の話をあえて聞いてみる
記憶を過信しない。メモや記録で補完する
- 「覚えてるつもり」よりも、「記録して確認」
- 重要な情報は、メールや写真、紙で残す習慣をつける
相手のスキーマを想像しながら話す
- 「この人はどんな経験をしてきたか?」
- 「どんな前提があるか?」を仮定して話す
まとめ:スキーマは理解のフィルターであり、誤解の発生源でもある
⭐️ 人はスキーマという「思考のテンプレート」によって世界を理解している
⭐️ しかしそのスキーマは、個人の経験や文化、感情によってまったく異なる
⭐️ 「何度説明しても伝わらない」原因は、スキーマのズレにある
⭐️ 他者理解の第一歩は、「自分のスキーマも偏っているかもしれない」と疑うこと
スキーマの違いは、誤解のもとであると同時に、多様な視点に触れ、学び合うための出発点にもなります。
「自分の常識は、きっと誰かの非常識」
そう意識して対話を重ねることこそ、これからの社会に必要な理解力なのではないでしょうか。
それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!