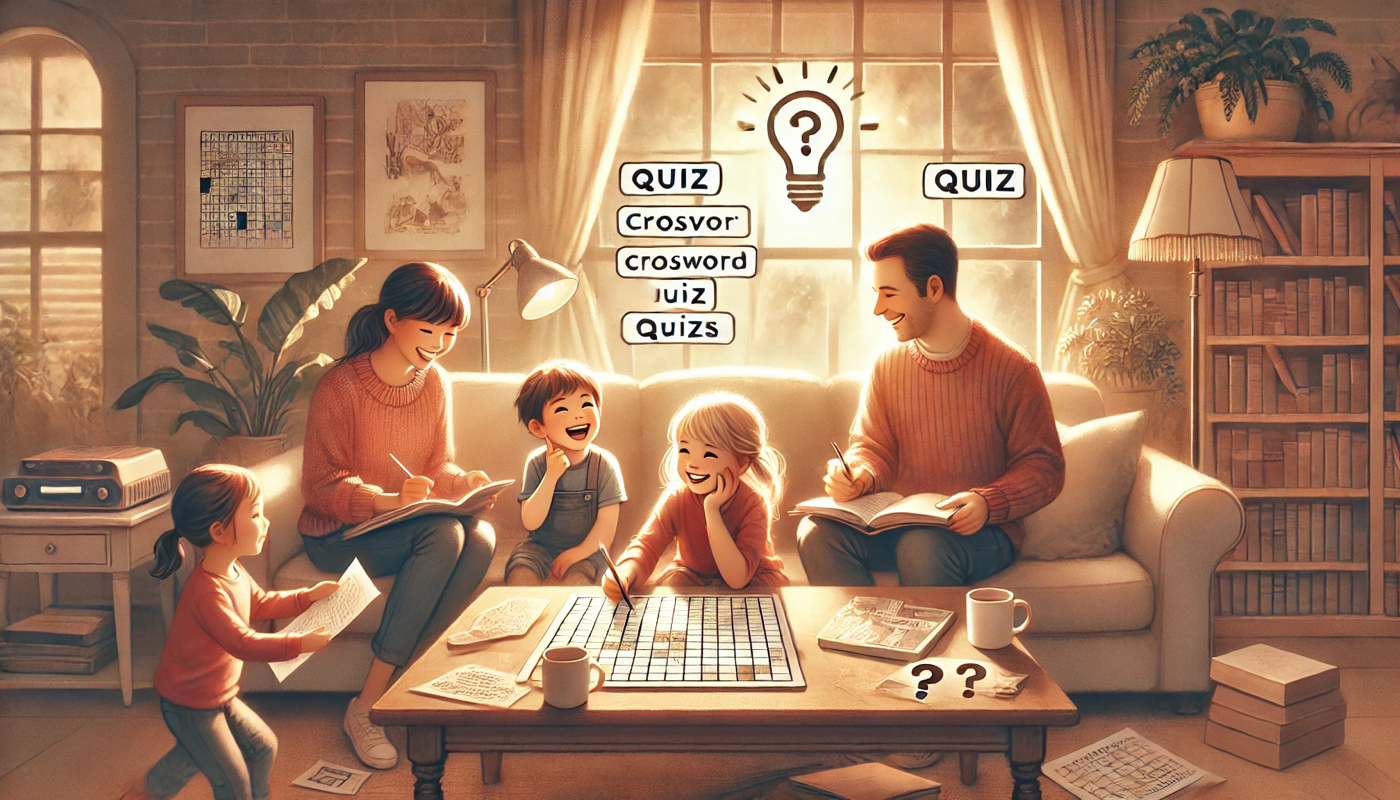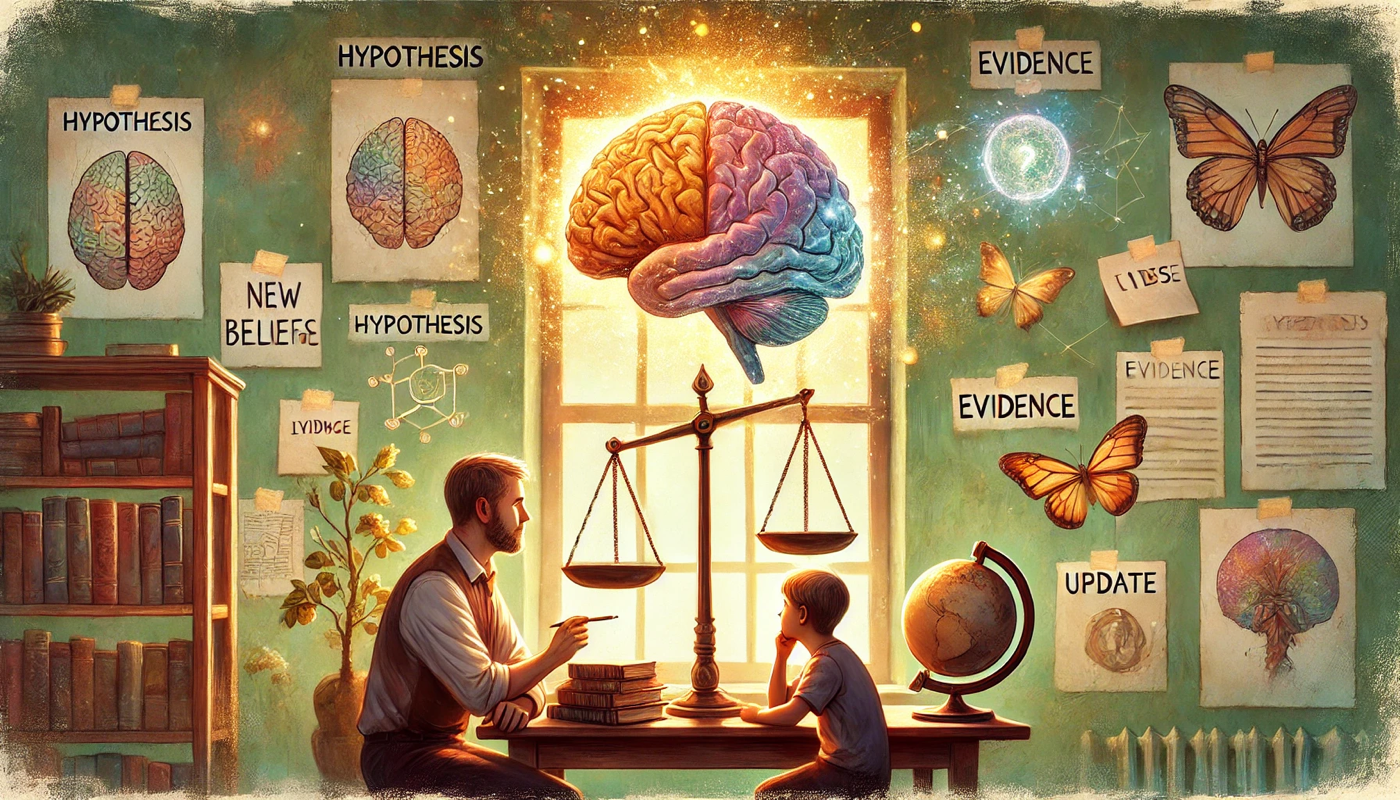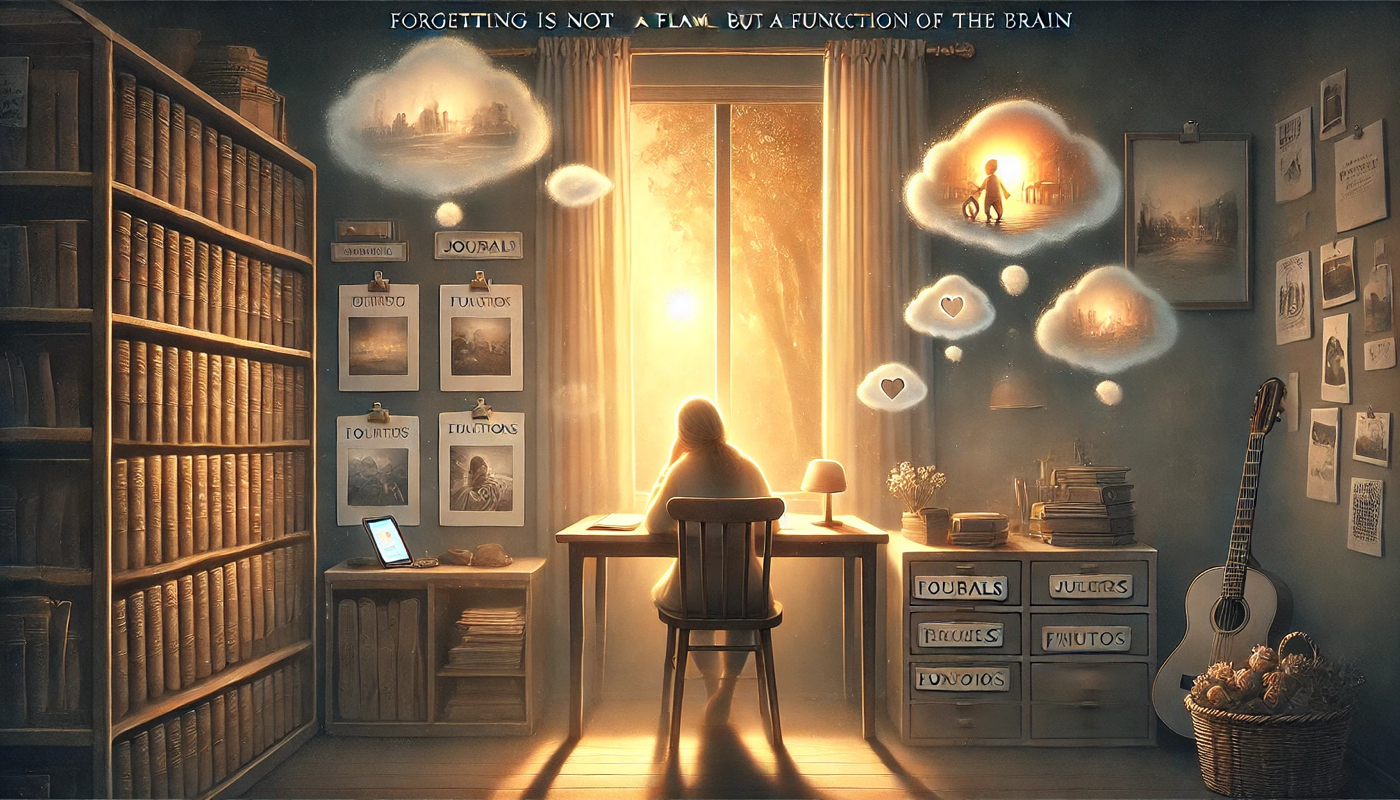褒めるのが先か叱るのが先か

今回の記事では、「褒めるのが先か、叱るのが先か?」という問いを軸に、「どんな伝え方が相手の成長を最大化するのか」を整理してみます。
この話のきっかけは、私自身が仕事で受けたフィードバックでした。
最初にガツンと指摘されてしまい、その後の褒め言葉を素直に受け取れないという経験がありました。
そこから「もしかして子どもや周囲の人にも、同じようなアプローチをしているのでは?」と気づきました。
どうすれば良い伝え方ができるのかを今回は掘り下げたいと思います。
目次
ポジティブ心理学から見た“褒める”重要性
褒められている状態で人は学ぶ意欲を高める
ポジティブ心理学の研究によれば、人はポジティブな気持ちのときに学習効果が高まるといわれています。
だからこそ、「最初に褒める → 次に指摘する → 最後にまた励ます」という流れが有効なのです。
先に肯定をもらうことで「自分には価値があるんだ」と思え、続く指摘も「成長のためのアドバイス」として受け止めやすくなります。
サンドイッチフィードバックの手法
ビジネスや教育界でよく使われる「サンドイッチフィードバック」は、まさに褒める→注意する→褒めるという順序。
相手が前向きに改善策を受け取り、“やってみよう”という意欲を抱きやすい仕組みです。
- ポジティブ枠: 「○○さんの発想、すごく面白いですね!」
- 改善枠: 「ただ、もう少しデータを入れると説得力が増すと思います。」
- ポジティブ枠: 「これができれば、さらに素晴らしい結果が出そうで楽しみです!」
なぜ“褒めてから注意”が効果的?
- 心理的安全性が確保される
- 頭ごなしに怒られると、自己防衛本能が働き「言い訳しなきゃ」とか「この人嫌だな」と感情的に反発しがち。でも、最初の一言が褒め言葉だと「この人は私を否定から入らないんだ」と安心でき、素直に耳を傾けやすくなる
- モチベーションを損なわない
- 最初に褒められれば、続く指摘も「自分をもっと伸ばすためのアドバイスだ」と受けとめられる。結果、「やってみようかな」という前向きな意欲に繋がりやすい
- 叱ってから褒めるだと逆効果
- 一方、先に「ダメ出し」されたうえで褒められても、「結局ダメなんじゃん…」というネガティブ感情が勝ってしまいがち。伝え方ひとつで、同じ内容が全く違う印象になるのは不思議ですが、心理的には大きな差があります
子育てや教育、職場でも役立つ
子どもの宿題や片付けで実践
「なんで宿題しないの!」と怒るのではなく、
- まず「昨日はプリントを自分から始めて偉かったね」「あの問題、難しかったけど挑戦してたじゃない!」と褒める
- そして「ただ、もう少し丁寧に字を書くとわかりやすいね」と指摘する
- 最後に「ちゃんと書けるようになったら、きっと先生にも褒められるよ! 楽しみだね」と励ます
これだけで、子どもの気持ちが全然違うはずです。
職場の後輩指導でも
「このレイアウト、見やすくていいね。ただデータが少し古いから最新のものに差し替えると、説得力が増すと思うよ。そこがクリアできれば、すぐに提案に活かせそう!」
こんなふうにサンドイッチするだけで、後輩も「改善点はわかったし、自分の良いところもちゃんと評価されてる」と感じられます。
“叱る”と“怒る”の決定的な違い
- 叱る: 相手のためを思い、冷静に指摘する
- 怒る: 自分の感情を相手にぶつける
アドラー心理学でも「他者は変えられない」という考えがあります。
強制ではなく、相手が“なるほど、ここを改善すればもっと良くなるんだ”と納得して自発的に行動するためには、褒める→指摘する→最後また褒める、というアプローチが理にかなっています。
暴力や怒鳴り声での指導は逆効果
バジル・バーンステイン(イギリスの言語学者)の言う制限コード(怒鳴り・威圧的な伝え方)では、子どもは理由を理解できず、応用がきかないまま育ちがち。
たとえば「いいからやれ!」という命令口調に従っても、子どもが“なぜそうする必要があるのか”を学べません。
一方、精密コード(物事を客観的・抽象的・人格的に述べる)のように「危ないからこうするんだよ」と理由を伝えるやり方なら、納得を伴う学びが得られます。
褒めるのが先か、叱るのが先か
- 先に褒めることで、相手の心を開き、自己肯定感を高めた状態で指摘を受け止めやすくする
- 最後にもポジティブな言葉を添えることで、「よし、やってみよう!」という前向きなモチベーションにつなげる
- 怒るのではなく叱る、「精密コード(理由を伝える)」を意識しよう
仕事でも子育てでも、たったこれだけのコツを守るだけで相手の成長意欲を引き出し、関係性を良好に保つことができます。
“褒めるのが先か、叱るのが先か”の答えは、間違いなく“褒める”が最初。
そして“叱る”際も冷静に理由を伝え、最後にまた背中を押す。
これが最高のコミュニケーションパターンなのです。
それでは、今日も1日、最高に円滑に生きましょう!