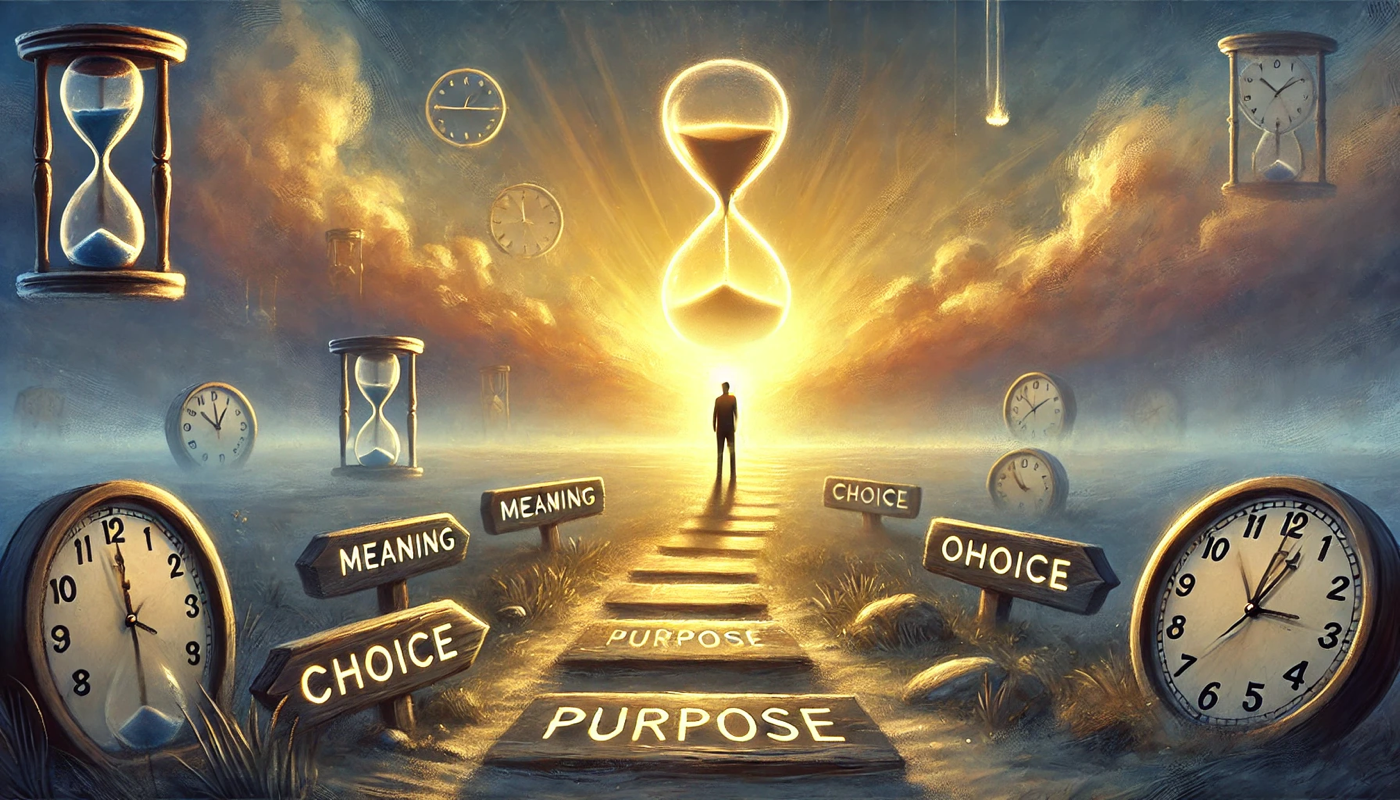人によって態度を変えるのは悪ですか?

「あの人、人によって態度を変えるよね」
そんな評価をされたら、ちょっと嫌な気持ちになる人は多いかもしれない。
上司にはペコペコ、部下には横柄、異性には優しく、同性にはそっけない。
そんな振る舞いを見て、不快感を抱くのはごく自然な感覚だ。
けれど、少し視点を変えてみたい。
そもそも、人によって態度を変えることは本当に悪なのだろうか?
誰しも、無意識のうちに相手に合わせて態度を変えている。
親しい人には甘えたり、初対面には礼儀正しく振る舞ったり、恋人には優しく、苦手な人には少し距離を取ったり。
そんなふうに、私たちは日々、関係性の中で自分を変えて生きている。
それは相手への配慮であり、時に自分の心を守るための防衛でもある。
「どんな人にも同じ態度で接する」ことは、一見美徳のように見える。
だが本当にそうだろうか。
たとえば、尊敬する人には丁寧な言葉を使い、長年の友人にはざっくばらんに話す。
それは相手との関係性に応じた調和であり、むしろ自然なことだ。
逆に、誰に対しても機械のように同じ接し方をする人がいたとしたら、それはそれでどこか不気味に感じてしまうかもしれない。
もちろん、あからさまなマウントや無礼は論外だ。
上には媚び、下には威張るという態度は単なる未熟さの表れであり、人間性の低さが露呈するだけだ。
だが、相手の立場や関係性に応じて態度を適応させるということは、社会の中で生きていく上で必要なスキルでもある。
職場や学校、家庭において、すべての人とフラットな距離で接するのは、むしろ不自然であり、ストレスの原因にもなる。
大切なのは、相手に合わせて自分を調整しながらも、自分の本質を見失わないこと。
柔軟でありながら、芯の通った人間であること。
そのためには、自分の内側にある「人格」というものを見つめ直す必要がある。
人格とは、私たちが社会の中で持っているさまざまな顔の集合体だ。
家庭での顔、仕事での顔、友人との顔、SNS上の顔、どれも偽りではない。
それぞれが私たちの一部であり、それぞれの場面に最適化された板のようなものだ。
ここで思い出したいのが「リービッヒの最小律」だ。
植物が十分に育つためには、必要な栄養素がバランスよく揃っている必要があり、その中で最も不足している要素によって全体の成長が制限されるという法則だ。
これを人の人格に当てはめてみると、ある一つの人格の板が極端に短いと、それが自分全体の魅力や信頼感を制限してしまうことがある。
たとえば、仕事では誰からも尊敬される立派な人格を保っていたとしても、家庭では家族に当たり散らすような振る舞いをしていれば、その短い板からこぼれ出る水のように、どこかでボロが出てしまう。
人格は繋がっている。
弱い部分を無視して他の部分だけを高めようとしても、どこかで限界が訪れるのだ。
だからこそ、大切なのは「すべての人格を磨く」こと。
それぞれの場面での自分を育て、バランスよく底上げしていく。
それは決して完璧な人間になれという話ではない。
昨日の自分よりも、ほんの一歩、どこかの人格を磨く努力をすること。
それが、やがて大きな自信や信頼へとつながっていく。
人によって態度を変えることは、恥じるべきことではない。
それは、変化の中で自分を守るための柔軟性であり、社会を生き抜くための適応力でもある。
ただし、その柔軟さの中に、自分の弱さを隠したり、他人を傷つけるようなズルさが入り込まないよう、私たちは意識的に「人格という樽」のすべての板を見つめ直し、育てていく必要がある。
どんな自分でもいい。
浅い自分、弱い自分、不器用な自分。
すべての人格の自分を愛し、育み、大切にしていこう。
誰かと比べるのではなく、昨日の自分より少しでも前に進むこと。
一歩でもいい。
人格の一枚の板でもいい。
それが、人生を豊かにしていく本当の「成長」なのだと思う。
それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!