血糖値の基礎知識を身につけよう
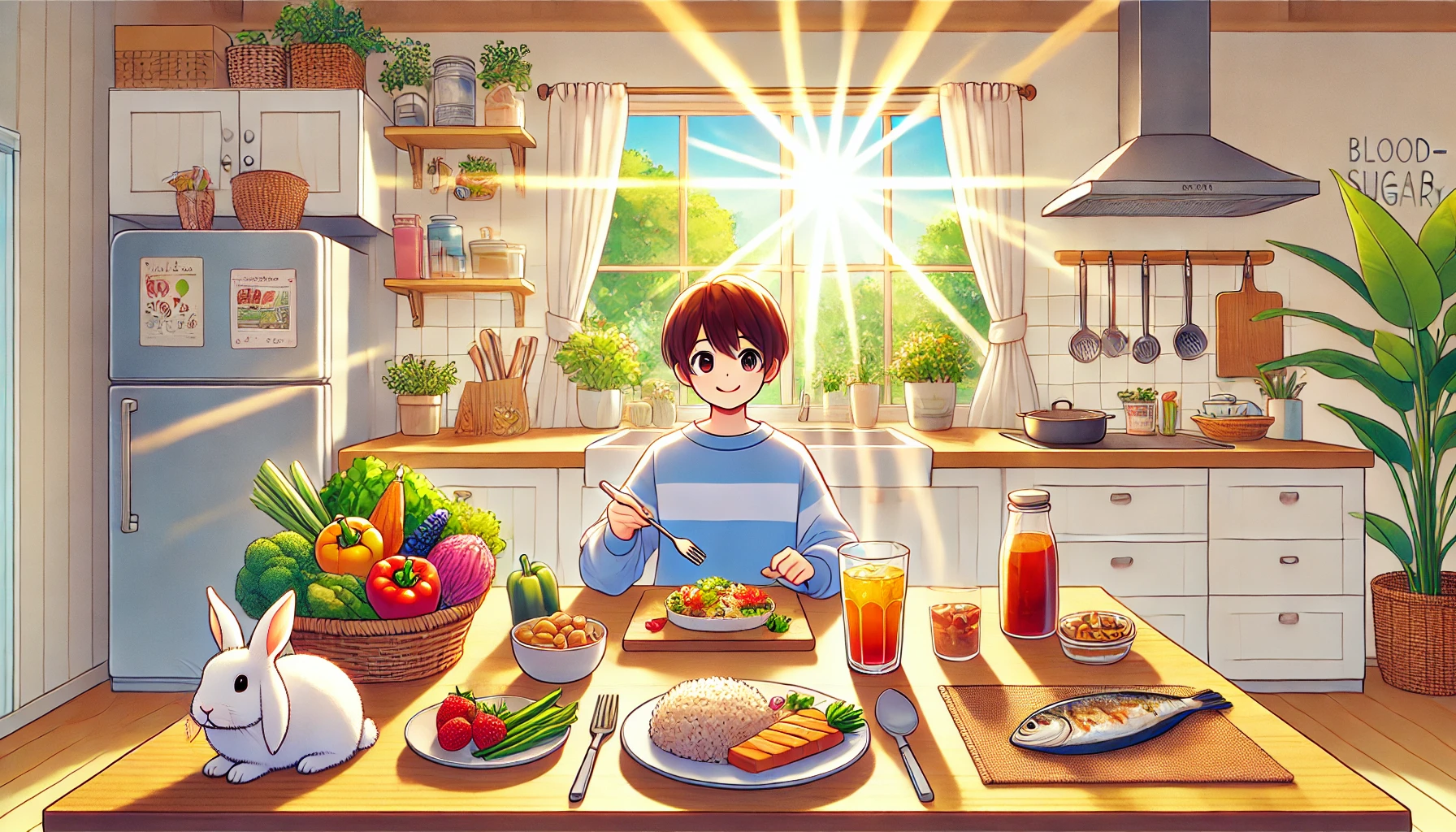
「昼食後に猛烈な眠気が襲ってきた」
「甘いものを食べたら元気になったけど、その後すぐだるくなった」
こんな経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
その背景には、いわゆる血糖値スパイクが潜んでいます。
日々の食生活で摂取している「糖」が体内でどのように消化・吸収され、血糖値に影響を与えているのかを理解することが、健康管理には欠かせません。
今回の記事では、糖の種類や血糖値変動のしくみ、そして急上昇を防ぐ具体策をわかりやすくまとめていきます。
目次
糖の種類と血糖値への影響
白米などの糖質(でんぷん質)
- 主な成分はでんぷんで、消化されると体内でブドウ糖に分解されます
- 白米やパンなどの精製された穀物はGI値(3章で詳細解説)が高めで、血糖値が急激に上がる傾向があります
- 玄米や全粒粉に変えると、食物繊維が多く吸収がゆるやかになり血糖値の急上昇を抑えやすいです
精製された砂糖(ショ糖)
- ショ糖はブドウ糖と果糖が結合したもの。消化吸収が速く、血糖値を急上昇させます
- 白砂糖を多量に摂取すると、砂糖クラッシュとも呼ばれる急降下(反応性低血糖)が起こりやすく、だるさや集中力低下につながることがあります
果物の果糖
- 果物に含まれる糖分の多くが果糖(フルクトース)。血糖値を直接上げるのはブドウ糖なので、「果糖そのものは急激な血糖上昇を起こしにくい」とよく言われます
- しかし果糖を過剰に摂ると、肝臓での代謝負担が高まり脂肪合成を助長する可能性があります。果物は食物繊維やビタミンを含むため、適量なら健康的ですが、果糖だからといって無制限に摂っていいわけではありません
ハチミツやメープルシロップなど自然由来の糖
- ハチミツやメープルシロップは果糖+ブドウ糖が含まれ、砂糖に比べるとミネラルなどの微量栄養素が豊富
- ただしカロリーや糖質としては依然高めなので、多量摂取すれば血糖値は上がります。甘味料として砂糖より多少マイルド程度の捉え方が無難です
結論:どの糖でも過剰なら血糖スパイクを招く
精製度が高いほど血糖値の急激な上昇が起こりやすいのは事実ですが、果糖やハチミツなら安全というわけではありません。
摂り方や食べるタイミング、食物繊維との組み合わせ次第で血糖への影響は変わってきます。
血糖値の急上昇(スパイク)はなぜ問題?
スパイクが起こるメカニズム
- 高GI食品や精製糖を摂る
- 血中ブドウ糖が急激に増え、インスリンが大量に分泌
- 短時間で血糖が急降下し、眠気やイライラ、過剰な空腹などが生じる
短期的デメリット
- 眠気、だるさ、集中力の低下
- イライラ感、メンタルが不安定になる
- 過食を招きやすい(すぐにお腹が空く)
長期的デメリット
- インスリン抵抗性の進行により、2型糖尿病や肥満のリスク増大
- 血管内皮を傷つけ、動脈硬化や心血管リスクを高める
- 認知機能やメンタル面への悪影響
GI値のしくみと血糖値コントロール
GI値とは?
- ブドウ糖を100とした相対値で、食品ごとに「血糖値上昇の速さ・高さ」を示す指標
- GI値が高いほど血糖スパイクを起こしやすく、低いほど上昇が緩やかになる
高GI食品 vs. 低GI食品
- 高GI:白米、白パン、砂糖菓子、ジャガイモなど(急上昇・急降下)
- 低GI:玄米、全粒粉パン、豆類、野菜、果物など(緩やかな上昇・下降)
低GI食品は食物繊維やミネラル、ビタミンが多い場合が多く、総合的に健康に有益。
血糖値の乱高下を防ぐアクションプラン
食べる順番を工夫する
- 野菜やタンパク質を先に食べ、炭水化物を最後に
- 食後血糖値のピークが低くなり、インスリンの過剰分泌を防ぐ
食材選びでGI値を意識
- 主食は白米→玄米や雑穀米、白パン→全粒粉パンに切り替える
- おやつはナッツやヨーグルトなど比較的低GIな食品を中心に選ぶ
よく噛んでゆっくり食べる
- 咀嚼を増やすことで吸収がゆっくりになり、満腹感も得られやすい。
- 一口30回を目安に咀嚼回数を意識してみる
食後に軽い運動
- 食後30分以内に5~15分のウォーキングやストレッチを行うと血糖値が急上昇しにくい
- 激しい運動である必要はなく、継続がカギ
過剰な甘味料に注意
- 白砂糖だけでなく、ハチミツや果糖も摂りすぎれば血糖値を大きく動かす恐れがある
- 使う量に気をつけ、食物繊維の多い食材と一緒に摂るなど工夫を
まとめ:血糖値管理で体も心も元気に
⭐️ 血糖値を安定させるメリット
- 食後の眠気やイライラが軽減され、日中のパフォーマンスが向上
- 生活習慣病を予防し、将来的な健康リスクを抑制
- メンタル面でも安定を得やすく、感情の乱高下が緩和される
⭐️ まずは小さなステップから
- 白米を半分だけ玄米や雑穀に置き換えてみる
- 間食の甘いお菓子をナッツ類にシフトしてみる
- 食後は必ず散歩を習慣づける
これら小さな工夫が、長期的には大きな変化につながります。
血糖値の急上昇と急降下は、体に余計な負担をかけ、日常生活のパフォーマンスに影響を与えます。
糖の種類(白米・精製糖・果物・ハチミツなど)を理解し、GI値の視点を持つだけでも、食後の不快症状や将来的な生活習慣病リスクをグッと減らすことが可能です。
「甘いものが大好きだけど、最近ちょっと疲れやすい…」と感じる方は、ぜひ今日から食事の順番を工夫したり、適度な運動を取り入れてみてください。
小さな習慣の積み重ねが、体と心を守る大きな力となるはずです。
それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!




